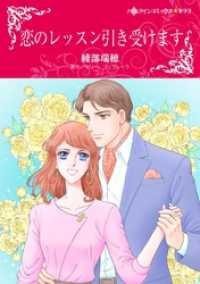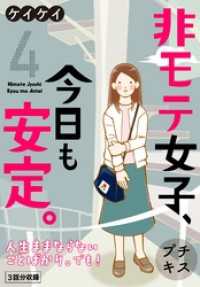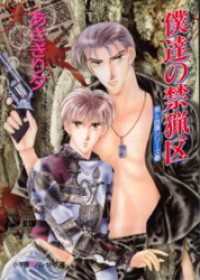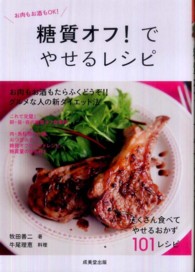内容説明
現代哲学が形成されるにあたってどれほど図像が中心的役割を果たしたことか、本書は17世紀の重要な人物たちを例に再構成を試みる。
目次
1 導入
2 展示品の劇場
3 パリの『思考遊び』
4 光と影のゲーム
5 数学的計算
6 感覚的認識と直感
7 化石、および大地の芸術理論
8 素描と下絵
9 生きた図書館としての図説アトラス
10 アカデミーとその劇場
11結び
著者等紹介
原研二[ハラケンジ]
1978年名古屋大学教養部ドイツ語講師。1981年ウィーン大学人文学部演劇学科留学(1983・9帰国)。1986年東京都立大学人文学部独文学研究室助教授。1996年東京都立大学人文学部独文学研究室教授。2007年大妻女子大学比較文化学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K.H.
6
「モナドには窓がない」で有名な『モナドロジー』は以前読んだけど、あまりものにならなかった。その程度のわたしだが、本書を読んで、ライプニッツってこんな人だったんだ、と驚いた。彼は何よりも「眼の人」だったとでも言えようか。そんな彼が終生こだわり、実現を夢見たのが「自然と人工の劇場」、今日風に言えば総合博物館。もちろん公共の博物館なんてない時代、本書序盤で個人のコレクションを渡り歩くライプニッツの旺盛な好奇心にはこっちまでわくわくさせられた。形而上学や数論が出てくる箇所は理解できたとは言い難いけど、良書だった。2022/04/17
EnJoeToh
5
ものすごかった。2012/03/04
theseus
4
本書は,万学にその業績を残した17世紀最大の巨人,ライプニッツの知られざる側面を扱う.ライプニッツが抱いた普遍的記号法の構想は,視覚情報および経験的想像力によって得られる知,すなわち表象知に対する懐疑と結び付けられて理解されてきた.しかし本書が主題的に扱う彼の「自然と人工の劇場」の計画は,ライプニッツが表象知に対しても最大限積極的な価値を見出していたことを明らかにする.それは「言葉と事物の一体化」に加え,「生きた印象の知識」を直視によって得る,普遍的博物館にして理想的実験室の計画であった.巻末資料も充実.2010/11/02
毒モナカジャンボ
1
ライプニッツが生涯をかけて取り組んだプロジェクト、「自然と人工の劇場」。人工言語の先駆であり数学的思考の権化たるライプニッツにとってさえ、記号の力は実物提示の力に及ばなかった。自然の戯れや芸術として化石や稀少自然物を見つめるとき、自然・人工・中間物の三領域を跨ぐ普遍実物提示教育の殿堂が立ち現れる。異様なバイタリティに満ちたライプニッツは現代科学システムの発端(何が科学が)から終端(科学をどう維持し広めるか)まで全てを一人でやり切る。インターネットの誕生により実現したかに見えた劇場だが、そこに神はなかった。2019/12/20
onisjim
1
視覚とイメージにあふれたライプニッツ論。モナドロジーや微分積分の人とクンストカマーがどう結びつくのか不思議だったが、こういう切り口があったとはね。楽しかった。2012/12/08