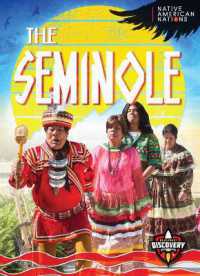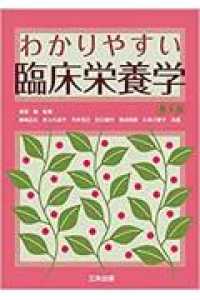内容説明
理想に燃え使命感にあふれた人を襲う病。需要が増加するヒューマン・サービスの領域において、近年大きな問題となっている仕事への意欲「燃え尽き」現象。その構造と原因、対処を心理学の立場から解説。
目次
1 バーンアウト研究の意義
2 ストレスとバーンアウト
3 バーンアウトの測定―マスラック・バーンアウト・インベントリー
4 MBIの展開とその他の尺度
5 バーンアウトのリスク要因
6 対処行動
7 バーンアウト研究の視点
著者等紹介
久保真人[クボマコト]
1983年京都大学文学部卒業。1988年京都大学文学研究科博士課程中退。1998年京都大学文学研究科博士(文学)取得。現在、同志社大学政策学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
cape
3
さっくり流し読みではありますが、バーンアウト=いわゆる燃え尽き症候群は対人職種を想定して生まれた概念であると知る。そして学術的には定義がきちんと固まらないままに言葉が一般に浸透していると。鬱とバーンアウトはどう違うのか?そうだよなぁ……と、HSPの盛り上がりとその是非をめぐる議論なども頭をかすめた。燃え尽き、ときくとあしたのジョーを思い出してしまうけども全然違いますね。2021/06/24
カラクリ
1
バーンアウトの測定方法の研究成果について詳細に記載されていた。バーンアウトを研究する人にとっては、バーンアウトの定義とその測定方法の標準化は非常に重要だと思う。が、バーンアウトになった(なりかけた?)自分としては、標準化には興味はなく、リスク要因や対処行動の方が興味深かった。特にバーンアウトからの回復過程はとても共感できた。 本書に限らず対人サービス業とバーンアウトの関係が語られることが多い印象。目的喪失とバーンアウトの関係についてまとめてある書籍はないものか。それともあまり関係ないのか?2018/04/07
あるる
1
全部読んでないけど卒論終わったのでとりあえず。 バーンアウト研究の歴史、要因研究、対処法研究などについて わかりやすい言葉・文章でまとめられていてとても読みやすい。 バーンアウト入門書として、バーンアウト研究したい人はとりあえず持っておきたい一冊って感じ。2012/02/12
_udoppi_
0
ヒューマンサービス従事者の臨床から生まれたバーンアウト概念の誕生と精緻化の過程、実証研究の蓄積、概念の拡大と希薄化などの研究史がふわっとわかる薄めの本。本書の結論では、バーンアウトは官僚制とは異なる職務特性(職務の複雑性・個別性、感情労働等)によって特徴づけられるヒューマンサービス組織を理解するための手段的概念として位置付けるべきとされる。要するに、心理学上のバーンアウトは、純粋に「燃え尽き」という現象を扱うための概念ではない(思ってたのと違った)が、剔抉された組織課題には参考になるところが多かった。2022/06/19