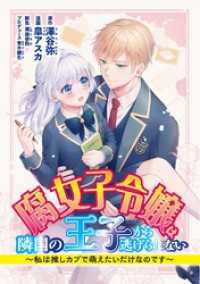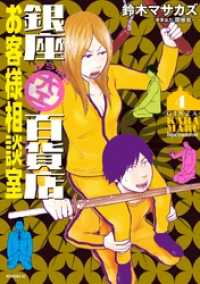出版社内容情報
ビーチイズムからギャルは生まれた。
かつて渋谷には、ヤマンバ、マンバなどと呼ばれた極端に肌を黒く焼いた「ガングロ・ギャル」がいた。彼女たちはどのようにして生まれ、そして消えていったのか。
戦後日本のメディア環境と日焼けスタイルの歴史から、ギャル文化の源流をスリリングに読み解く!
2020年代現在、メディアを席巻するギャル文化の源流は、90年代からゼロ年代にかけて渋谷に特異点のようにして現れた「ガングロ・ギャル」にある。
彼女たちはなぜ、突如現れたのか? 90年代、デジタル・テクノロジーが大きく発展し、コミュニケーションの場がリアル空間からバーチャル空間へと移行する中、渋谷を砦にリアル・コミュニケーションの美意識を最後まで守ろうとしたのが彼女たちだった。その後、世界はバーチャル・コミュニケーション中心の新しい時代を迎え、ガングロ・ギャルは消えた。彼女らが残した記録と証言、新しいコミュニケーション・テクノロジーを詳細に取材し、「ビーチイズム」からギャル文化の成立を大胆に読み解く。
内容説明
ビーチイズムからギャルは生まれた。かつて渋谷には、ヤマンバ、マンバなどと呼ばれた極端に肌を黒く焼いた「ガングロ・ギャル」がいた。彼女たちはどのようにして生まれ、そして消えていったのか。戦後日本のメディア環境と日焼けスタイルの歴史から、ギャル文化の源流をスリリングに読み解く!
目次
序章 インターネットのせい
第1章 ガングロ・ルックの源流(フランス・ガングロ・ルック;カリフォルニア・ガングロ・ルック;東京・ガングロ・ルック)
第2章 渋谷・ガングロ・ルックの変遷(一九七〇年代後期の渋谷・ガングロ・ルック―サーファー・陸サーファー;一九八〇年代中期の渋谷・ガングロ・ルック―ロコガール;一九九〇年代初期の渋谷・ガングロ・ルック―ポスト・ロコガール;一九九〇年代中期の渋谷・ガングロ・ルック―コギャル;一九九〇年代後期の渋谷・ガングロ・ルック―ガングロ;二〇〇〇年代の渋谷・ガングロ・ルック―ゴングロ・ヤマンバ・マンバ)
終章 ハロウィンの渋谷
著者等紹介
久保友香[クボユカ]
1978年、東京都生まれ。2000年、慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業。2006年、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了。博士(環境学)。専門はメディア環境学。東京大学先端科学技術研究センター特任助教、東京工科大学メディア学部講師、東京大学大学院情報理工学系研究科特任研究員など歴任。日本の視覚文化の工学的な分析や、シンデレラテクノロジーの研究に従事。2008年『3DCGによる浮世絵構図への変換法』でFIT船井ベストペーパー賞受賞。2015年『シンデレラテクノロジーのための、自撮り画像解析による、女性間視覚コミュニケーションの解明』が総務省による独創的な人向け特別枠「異能(Inno)vation」プログラムに採択(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
史
Yasuhiko Ito
caniTSUYO
らすた
マヌタ