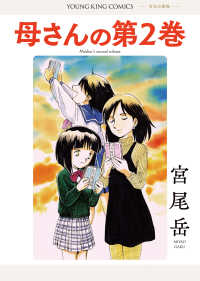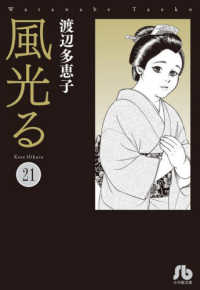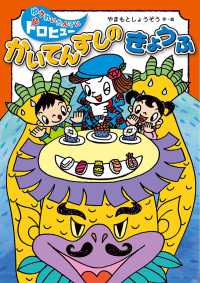出版社内容情報
西本昌司[ニシモトショウジ]
著・文・その他
内容説明
都会の真ん中で「すごい石」を探す。丸の内のビル外壁にマグマの痕跡を見る。日本橋のデパートでアンモナイトを発見!?石に秘められた人と地球の物語を掘り起こす、都市型“発掘”エンターテインメント!
目次
1 街角地質学とは何か?―石材を見て楽しむ基礎知識(東京の街を彩る石の生い立ち)
2 人間の営みを感じる石めぐり―石材でたどる日本近代化の歴史(近代的な石材利用のはじまり(明治)
華やかな石材の時代(大正~昭和初期)
現代における石材の多様化(戦後))
3 地球の営みを感じる石めぐり―石材でたどる大地の歴史(日本列島成立後にできた石;化石でたどるテチス海の生物;大理石の模様からたどる大地の変動;造山帯でできた御影石;マントル上昇流で生まれた個性派御影石)
著者等紹介
西本昌司[ニシモトショウジ]
“街角地質学者”。名古屋市科学館主任学芸員。博士(理学、名古屋大学)。専門は、岩石学、地球科学、博物館教育。1966年広島県三原市生まれ。筑波大学第一学群自然学類卒。同大学院地球科学研究科博士課程中退(前期課程修了)。名古屋大学博物館研究協力者、愛知大学非常勤講師、NPO法人日本サイエンスサービス理事、その他各種委員を兼務。地球科学の振興に努めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kk
20
再読。以前図書館で借りて読みましたが、とても興味深かったので購入して再読。我ながら何にそんなに惹かれるのかよくわかりませんが、石材の奥深さにすっかりやられてしまってます。この本と石材事典を手に、東京の街を観てまわろうと思います。2024/02/18
コーデ21
20
都内の建築物に使われている「すごい石を探す」という視点がとても新鮮☆彡 著者の地質学的な豊富な知識と限りなく熱い「岩石愛」には圧倒されました。ここ数年、都内の近代建築散歩を趣味としているので国会議事堂やトーハクや国立科学博物館、日本橋高島屋・三越等に色んな石材が使われていることは見知ってはいたものの、これほどに多種多様な石が使われているとは驚き!今後はこの本を携えて「宝探し」(笑)的視点で改めて建築巡りをしてみたいと思ってます🎵2022/07/05
宇宙猫
20
★★★★ 壁や床に使われている石の本。ビルの壁とか見るのが好きなので嬉しい。昔は化石が入ってるのをよく見たけど、最近は石材自体を使ってない気がする。”石材と地質学の分類が一致しないのは当然。地質学の方が新参だから偉そうなことは言えない”目から鱗。石のでき方が分かったのは人類の歴史的に見れば最近だよね。”偽化石”シダの化石に見えるが、岩の割れ目にできた結晶。びっくり”貝化石がつくる模様”砂浜の二枚貝が殻を伏せた向きになっている事から上下がわかる。ちょっとしたことから色んなことが分かるのがサイエンスの楽しさ。2020/04/04
kk
18
図書館本。都庁、国会議事堂、絵画館や明治生命館など、都内の名だたる建物を引き合いに出しつつ、その内装や外壁に使われている石材の特徴や地質学的な背景などを語るもの。石好き、地学好き、散歩好きには堪えられない一冊。以前に購入した『原色 石材大事典』を参照しながら楽しく読みました。かくなる上は電子書籍版を必ず購入し、東京の街を今までとは違った目線で見て歩かなければなりませぬ。とは言え、この本、石とか建築石材とかに興味のない向きには、全く面白くないこと間違いなしかも。2023/08/13
RASCAL
18
タイトルは「地質学」ですが、ほぼ全編、建築物に使われている石材の話。外装材としての花崗岩など、内装材としての大理石が、マニアックにも国内外の産地別に紹介されている。もう少しブラタモリっぽいものを想像していたのだが、思っていた内容とちょっと違った。2020/07/05
-
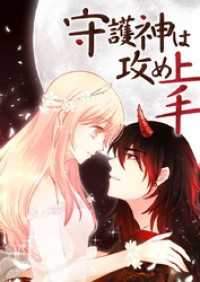
- 電子書籍
- 守護神は攻め上手【タテヨミ】第91話 …