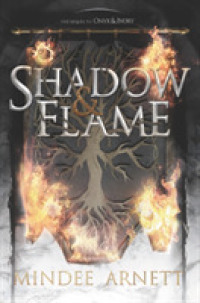出版社内容情報
安田喜憲[ヤスダヨシノリ]
著・文・その他
内容説明
湖の底に静かに堆積し、長い年月をかけて美しい縞模様を刻んできた「年縞」、それは地球の記憶そのものだった。過去の標準時計として、世界から認められた日本の年縞が、次々と新たな事実を明らかにしていく。危機の時代を生き抜いた生存戦略とは―「年縞環境史学」が解き明かす人類史の謎。
目次
第1章 「年縞」という画期的な年代測定法の発見
第2章 大洪水・高潮・暴風雨・豪雪・気候大変動の時代
第3章 土器と稲作がもたらした一万年という時間
第4章 麦作と牧畜から始まる破壊の歴史
第5章 縄文土器から生まれた心
第6章 危機を乗り越える縄文人の知恵
第7章 生命文明の時代へ
第8章 日本が立ち上がるために
著者等紹介
安田喜憲[ヤスダヨシノリ]
1946年、三重県生まれ。東北大学大学院理学研究科博士課程退学。理学博士。国際日本文化研究センター名誉教授。東北大学大学院環境科学研究科教授。2007(平成19)年紫綬褒章受章。気候変動と人類の生活・歴史の関係を科学的に解明する「環境考古学」の確立者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tako
1
完熟しても落ちない種を持ったものを選んで今のイネができたそうです。 確かに、落ちずにそのまま残っていますよね。2014/04/05
そらのひつじ
1
著者は、福井県水月湖でのボーリング調査で得られた堆積物から一万年以上前の気候変動を季節単位の精密さで調べる手法を開発し、今やそれは世界的な地質学の基軸となっているらしい。そんな第一線の研究者による、一万年以上のスケールでの歴史観が圧巻だ。気候変動で死に逝くマンモスや幼くして亡くなった我が子の足形を形見とする縄文人など、読んでいて目が熱くなる想像力を駆使した記述もすばらしい。縄文時代は文明以前の未開の時代ではなく、人同士で争うことなく自然と共生する文明の時代だったとの主張には、目を開かされた思いだ。2014/02/20
hal
0
年縞で過去の自然環境の変遷を、高い精度で再現する、その基準が福井県の水月湖になっていることは知らなかった。著者の縄文時代に学べという主張には賛成するが、縄文時代を過度に美化している気もする。本当に縄文時代には戦争はなく、持続的な思考で生活していたのだろうか?2017/05/12
ハイパー毛玉クリエイター⊿
0
終盤、著者のテンションがあがってしまったせいか、個人的な思想ややや宗教じみた記述が散見し、ほんのすこ~し胡散臭い。が、年稿の研究に関する解説の数々はすばらしく、とても興味深かった。1万年以上もの時をさかのぼり詳細な環境を復元できるというのはどえらいことである。そんな奇跡の堆積物がこの日本に存在したという点にも感動をおぼえた。年稿をめぐる調査・研究は「人類とは何か」「日本人とは何か」とアイデンティティを問いかける旅のようですらある。ちなみに著者は年稿という言葉の生みの親でもある。別の著作も読んでみたい。2015/08/06
rubyring
0
日本に今のような気候が誕生した時期や、土器作りをはじめとする縄文文明が誕生した時期を知った。この本を読むことは、数種類の言語が融合したと思われる日本語が誕生した背景や、精霊信仰のような信仰心が残り続けている背景を推測するために役立ちそうである。
-

- 電子書籍
- 龍馬伝 III SEASON3 RY…