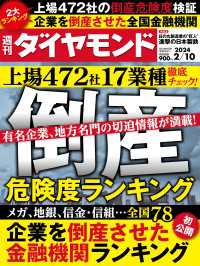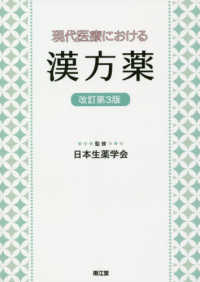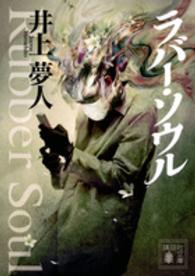目次
1章 「差別問題」から「欲望問題」へ(少年愛者の「痛み」;差別というくくりへの違和感;カミングアウトの意味付けの変化 ほか)
2章 ジェンダーフリーの不可解(ヘテロ・システム、「性別二元制」;「中性化」は誤解なのか?;保守派vsジェンダーフリー ほか)
3章 アイデンティティからの自由アイデンティティへの自由(「枠付け」からの自由;アイデンティティの内実の変化;共同性を成り立たせる根拠 ほか)
著者等紹介
伏見憲明[フシミノリアキ]
作家。1963年東京生まれ。武蔵野音楽大学付属高校・声楽科卒。慶應義塾大学法学部卒。1991年、『プライベート・ゲイ・ライフ』(学陽書房)でデビュー。独自のジェンダー/セクシュアリティ論を提出し、状況にインパクトを与える。以後、ゲイムーブメントの先駆けとしてメディアにしばしば登場し、全国を講演などで駆け回る。2003年には、初の本格小説『魔女の息子』(河出書房新社)で第40回文藝賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
寛生
36
【図書館】恐らく初めての伏見さんの本。「命がけで書いたから、命がけで読んでほしい」というエピローグ。大学生向けの授業にいいと思う。丁寧に議論をされていているという印象は持つものの、どこかで畏れのようなものがあるんじゃないかと匂う(笑)。「少年愛者の『痛み』」とういタイトルで始まる本書は、自身の少年愛という欲望と法律・社会との関連性について言及しながらも、「ハッテン場」を「風俗」と呼び(153)、「共同性」という言葉がやたらに繰り返されている。ちょっと臆病すぎる。良書。2014/09/09
みのくま
8
ゲイである著者が性的マイノリティを「差別問題」ではなく「欲望問題」として捉え直そうとする本書。欲望とは不満や痛みや欲求や理想を抱く事であり、社会が各人の欲望をできるだけ実現できるよう調整する事が望ましいと主張する。これが「差別問題」としてしまうと、差別の根源である性差の解消が目的となってしまうきらいがあるのだ。差別の解消は確かに重要ではあるのだが、性差そのものは自然であるためその解消には多大なコストが掛かる。と、要約してみたが本書の最大のポイントは、当事者主義の否定、脱正義によるマイノリティ擁護なのである2019/02/11
西澤 隆
5
未成年同性愛嗜好者が必死に「本当にやったら犯罪だから絶対我慢」と強く自制する告白からはじまる冒頭が衝撃的。まず「ニヤニヤしている異常性癖者の享楽」的ではない例を提示することで読み手の立ち位置を断罪者から「もしかしたら自分も当事者たり得るかも」と調整した上で進める話は「あるべき論」とははなれたかなり身も蓋もない話。ただ、こういう話は身も蓋もない話を検討しなければ意味のある答えを探すことは難しいわけでこういった議論が言葉狩りなく進められるのは大切なことだと思う。評論家的な関わり方から離れるためのきっかけの一冊2023/08/22
まあい
3
2007年の本。セクシュアリティをめぐってネット上で日々行われている不毛な議論は、いまだにこの本の地平を越えられていない。賛否両論あるだろうが、いかに他者を説得して社会を変えるか、と考えるならば重要な一冊となるだろう。はっとさせられるところは多い。2017/01/05
oko1977
3
筆者自身の運動半生を基に、自らの欲望を社会とどう折をつけていくかの問題を述べた本。本書はセクチュアルについてであるが、ネット社会がまずます進み、個人の発言力が高まっていくこれからにあたっては、個人の様々な欲望が社会と衝突していくとはますます増えていくと思う。そういったときに、豊かな社会にしていくための、発言者と社会側の行動指針としても一読にあたる。さすがに一線で長年運動してきただけあって、筆者の意見はバランスがとれていて現実味がある。2008/02/20