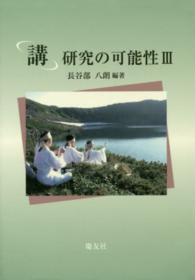目次
序章 戦後保育実践への招待
1章 敗戦から一九五〇年代―戦後保育実践の出発
2章 一九六〇年代―伝えあう保育の開花
3章 一九七〇年代―あそび保育の発展
4章 一九八〇年代―多様な保育の創造
5章 一九九〇年代―共感を育てる保育の深化
6章 二〇〇〇年以降―父母とともにつくる保育の展開
終章 いま、保育実践史に学ぶ意味
著者等紹介
宍戸健夫[シシドタケオ]
同朋大学客員教授
渡邉保博[ワタナベヤスヒロ]
静岡大学
木村和子[キムラカズコ]
名古屋短期大学
西川由紀子[ニシカワユキコ]
華頂短期大学
上月智晴[コウズキトモハル]
京都女子大学短期大学部(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
24
戦後の保育実践記録の紹介と解説をとおして、保育実践がどのように創造されてきたのかを考察した本です。とても貴重な記録が掲載されており、勉強になりました。戦後の保育実践が、子どもたちの何を大切にして行われてきたのか、現場の保育者たちは何に格闘・模索してきたのか学ぶことができました。保育実践史という研究分野はまだまだ確立されてきたものではないかもしれません。しかし、歴史的な知見がなければ今日の保育実践の問題を豊かに解決していく、将来を見通すということは難しいでしょう。実践記録は生きた研究素材なのだと思いました。2017/08/30
-

- 洋書電子書籍
- Ethical Case Studie…
-
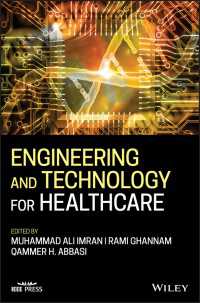
- 洋書電子書籍
- Engineering and Tec…