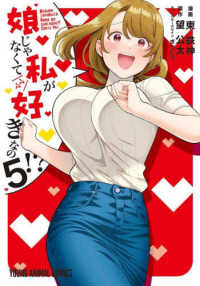内容説明
「ゲド戦記」の翻訳者。児童文学にしなやかなまなざしを向け、日常の不思議におどろき、善き人たちとの邂逅をつづる著者のエッセイを、はじめて集成する。三十余年にわたり若い人たちに語り続けた大学での、「最後の授業」も収録。
目次
世界の不思議にふれた日々
最後の授業「なぜ本を手ばなせなかったか」
人生って…
凡庸に着地すること
子どものときに…
世界との幸福な出会い
自由になりたかった
教室はわからなくてはいけないところ?
青年という季節・現代青年の生き方
追慕三景〔ほか〕
著者等紹介
清水眞砂子[シミズマサコ]
1941年、北朝鮮に生まれる。児童文学者・翻訳家。2010年3月まで青山学院女子短期大学教授。おもな著作に、『子どもの本のまなざし』(洋泉社、日本児童文学者協会賞受賞)など。訳書に、アーシュラ・K・ル=グウィン「ゲド戦記」(全6巻、日本翻訳文化賞受賞)ほか多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
魚京童!
18
日常を散策されてた。日常って大体たいしたことがないんだよね。だから日常で、非日常を求めているからよくないんだよね。毎日が退屈であるなら、どこかで花火を打ち上げたい。でもそんな毎日の中に良さを見つけるべきだという意見もあるし。何とも言えないよね。でも言えるのは、いまみたいに数週間ごとに戦争と平和が繰り返されるのは苦手。平和に浸ってから退屈な日常の中に良さを見出し始めたころ戦争が始まる。振り回されて退屈を感じるようになる。良くないよね。2019/03/10
joyjoy
5
「高を括るのではなく憧れることを、見限るのではなく共感することを、子どもの私は本を通して学んだ…」「子どもたちが何を言わないでいるかに周りの大人がもう少し注意深くなったら、彼らの持つ慎ましさを私たちもいま少し共有できるのでは…」「平和を生きのびるために…驚くという才能。驚きをもって世界と対峙した喜びの記憶を、そして、そのとき手にした問いを手ばなさないこと。すなわち希望を手ばなさないこと…」などなど、心に残る言葉がたくさんあった。2020/02/26
波多野七月
5
「子ども時代の私にとって、本は窓だったのだと思います」この一文に、たとえようもない程に心がふるえた。『ゲド戦記』の翻訳で知られる著者が紡いだ、凛とした言葉達。本への思いや、読書体験への幾つもの思い出達。そして児童文学作品への強い思い。それらを表現する語彙の豊かさと、その様式美が素晴らしい。大学の講義等で語られた内容もあるため、決して一般向けの読み物ではないのかもしれない。けれど、どうか1人でも多くの読者にこの書物が届いてほしいと願わずにはいられない。2013/10/15
ロピケ
4
私にとってこの本の一番の読みどころは「虚構の愉しみ―モモとゲド」。私も「細部の、一見無駄とも見える書き込みによって」「日々の暮らしを生きるように、五感をいっぱい目覚めさせて」「物語世界を生きていくことができる」物語を読みたい。ただ、エンデの本も完璧ではないかもしれないけど、『はてしない物語』(映画『ネバーエンディングストーリー』しか見ていないけど)バスチアンが屋根裏部屋みたいなところでマットレスを被って、本を読むシーンが(時々、自分で真似するくらい)大好きだ。読んでないけど、まさか本にこの場面、あるよね。2024/08/06
三月★うさぎ
3
彼女の翻訳は堅苦しくて苦手だ。一度だけ聞いた講演会でも厳しそうな人だと思った。この本を読んでも同じことを思った。それでもこの本に収められたら文章から射す光がチラリと私の心を照らす。何故自分が「本を読むのか/読んできたのか」がストンと納得できた文章もあった。子供の頃、何もかも忘れて本を読んでいた気持ちを思い出した。大きな収穫だ。2010/11/14
-

- 和書
- 香取慎吾まるごと百科