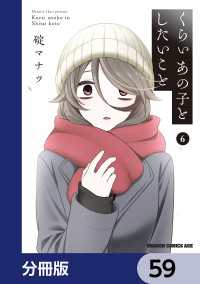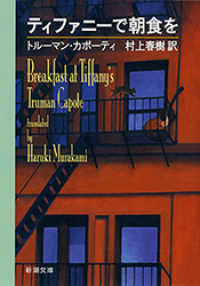出版社内容情報
秀吉の「首都」伏見城下の姿、消された巨大湖「巨椋池」の物語、寺田屋に代表される船宿の実態、名産の日本酒のブランドと酒米……。
京都の水運のかなめ、伏見の歴史と文化を掘り下げる、シリーズ第6弾。
内容説明
秀吉の「首都」伏見城下の姿。歴史に消えた巨大な巨椋池の物語。寺田屋をはじめとする船宿の実態。伏見名産・清酒のブランドと酒米…京都の水運のかなめ伏見の歴史文化。京都の文化資源発掘シリーズ第6弾。
目次
1 伏見の位置と交通(街道と舟運の交わるところ;京街道の宿場町にのこる「船宿」―伏見の寺田屋と枚方の鍵屋)
2 深草遺跡の意義、一五世紀の「伏見」(深草遺跡からみた弥生文化の東西交流;『看聞日記』から見る一五世紀前半の伏見)
3 伏見城と城下(秀吉の「首都」伏見)
4 近現代の伏見(「伏見義民」と明治維新―「伏見義民伝」受容と顕彰・考証活動;伏見酒蔵群のブランド構築における米の価値;「巨椋池」についての物語が成立する過程について)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
わ!
7
枚方宿の鍵屋資料館へ行った時のことである。鍵屋資料館へは何度か拝見させていただいているが、数年ぶりに中へ入ってみた。するとこの本のコピーが展示台の上に置かれていた訳である。「この本は「伏見」の本のはずでは…」と思いつつ、内容を読むと、伏見の船宿に対比する形で枚方宿の鍵屋の歴史が書かれていたのである。まったく思い出せなかった…で、やむを得ず読み返してみた訳である。一通り読み直し、当然覚えていた箇所もあったのだが、自分の記憶力の乏しさに愕然とした訳である。2025/07/18
わ!
2
「京都を学ぶ」というシリーズ本の最新刊だが、私に言わせていただくと、伏見という場所はやはり京都ではない。いやまぁ、住所で言えば、京都市伏見区なのであるが、昔は京都市とは別に伏見市として独立していた時期も(わずかではあるが)あったし、何より伏見には「京橋」があるのである。だいたいの都市に於いて、京都へ向かう街道へかかる橋が「京橋」となる。伏見が京都ならもはや京都内部にいるのだから、京橋が造られる必要もないのだろう。この本では「伏見義民」や「巨椋池」に関して「種明かし」がされているのが面白かった。2022/06/06