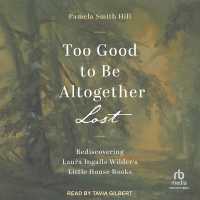内容説明
ネイティブアメリカン、マイノリティ、フェミニズム…、基盤となる世界観の拡張がオルタナティブな科学の扉を開く。
目次
序―「その問いは誰のものか?」
未完の科学
地図、モデル、科学の統一性
科学は価値観の宝庫
科学者の属性を反映する科学
文化と文化研究の諸問題
心理的距離と自然の概念
心理的距離、視点取り、生態学的関係
複雑化する文化モデル―心理的距離の限界
これまでの議論
インディアン教育略史
文化に根差した科学教育は複数の認識論を導く道標
メノミニーを事例とするコミュニティに根差した科学教育
コミュニティに根差した科学教育―AICの焦点
コミュニティでの協力関係―いくつかの成果
要約、結論、示唆
著者等紹介
山田嘉徳[ヤマダヨシノリ]
1986年生まれ。関西大学大学院心理学研究科心理学専攻博士課程後期課程修了。博士(心理学)。大阪産業大学全学教育機構准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Junya Akiba
1
科学と文化的背景、そして、科学教育について。ネイティブアメリカンたちと白人の科学(物質的で唯一の解を求め、我々が現代的な科学と思うもの)の関わりをネイティブアメリカンの目からひも解く。確かに論理的/演繹的、帰納的で再現性を基に形作られた現代科学に慣れるとそれが心地よくなってしまい、著者のいうようなそれぞれの文明・文化に根差した“科学の多様性”には気づきにくくなっていますね。しかし、社会科学ならず自然科学も研究者の文化的背景や直観の影響が及ぶことは、古くはアインシュタインの幾つのかの言動からわかります。2024/05/13