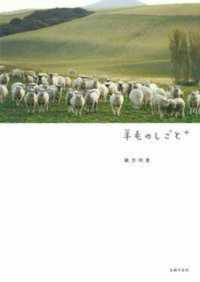- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
内容説明
早期に学校から離脱する若者たちに対して各国はどのような対策をとっているのか。政策実態を基に予防、介入、補償という観点から検討する。
目次
学校から離れる若者、多様な学び方と教育訓練の場
第1部 総論(学校教育制度における「早期離学」の問題性認識;OECDによる早期離学の予防・介入・補償政策;EUによる早期離学に関する教育訓練政策の展開)
第2部 各国編(イギリスにおける早期離学への対応とニートへの支援;フランスにおける早期離学対策の多様性とその課題;ドイツの早期離学問題―就学義務の正当性と射程;オランダにおける早期離学の現状と課題;スペインにおける早期離学問題に対する教育制度上の対策と限界;スウェーデンの離学予防・復学支援施策;ノルウェーにおけるドロップアウトの問題と修了率向上政策;EU新規加盟国にみる早期離学の多様性と共通性)
「離学」の意味をノンフォーマル教育から問いかける
ヨーロッパから俯瞰してみた日本の学校社会
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう
3
本書では、後期中等教育を離れる若者への支援について、ヨーロッパ各国の教育政策が論じられている。早期離学が問題視されるのは、就職が困難になり、ひいては国の経済発展の停滞につながるためである。また、本人の生活能力や職業能力の向上が阻害される点も懸念される。ヨーロッパでは、多様な教育環境を提供し、特に職業訓練校(日本でいう工業高校や農業高校のこと?)の割合が高い。これにより、資格取得を重視し、早期離学者も再び職業訓練を受けられる仕組みを整えている。しかし、学校が労働人材の育成に偏る傾向も指摘されている。2025/04/03