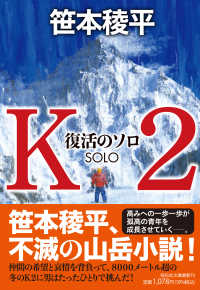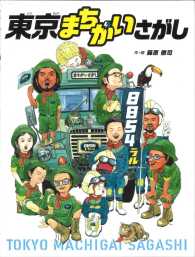内容説明
『資本論』研究の新展開のために。「労働する諸個人」「物質代謝論の可能性」「将来社会への社会的陶冶」の三つの観点から、マルクス『資本論』の可能性を再考する。
目次
社会的陶冶論からの提起
第1篇 労働する諸個人(グローバリゼーションにおける自由な諸個人の陶冶;労働を基礎とする社会把握―「生産」概念の再検討を通じて;富と貧困、資本と賃労働、そして「主体形成」)
第2篇 物質代謝論の可能性(人間と自然の物質代謝と生活の再生産;生産力発展と物質代謝の合理的規制)
第3篇 将来社会への社会的陶冶(社会的陶冶論としての『資本論』;資本における物象化と労働主体の陶冶―『資本論』における物象化論の位置;独自な資本主義的生産様式と労働者階級の存在論;マルクスと歴史的運動―現代マルクス派の「社会運動」把握の手掛かりとして)
著者等紹介
鈴木敏正[スズキトシマサ]
1947年生まれ。北海道文教大学教授・北海道大学名誉教授。教育学
高田純[タカダマコト]
1946年生まれ。札幌大学名誉教授・旭川大学教授。哲学・環境倫理学・社会思想
宮田和保[ミヤタカズヤス]
1951年生まれ。北海道教育大学名誉教授。社会経済学(マルクス経済学)・言語論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sayan
24
タイトルの「21世紀」と「陶冶」に引き付けて資本論の新たな読み方か、と期待したが同時代のリアリティを盛り込んだ議論がほとんどなく戸惑う。例えば、本書では「(現在、労働者が直面する課題克服のために)彼らの能動性を回復し、持続させるのは労働組合」と言う。数日前に読了したM・ディビスの書籍「マルクス古き神々と新しき謎」では、労働組合の問題解決能力に限界があると提示し、いま労働者は非正規等、不安定な状態にあり連帯する余力がない、とする。この部分だけ比較しても、両書籍が同じ時代に資本論を議論しているとは考えにくい。2020/09/30