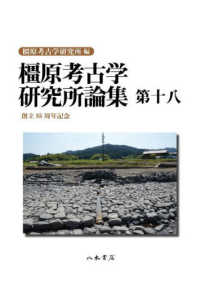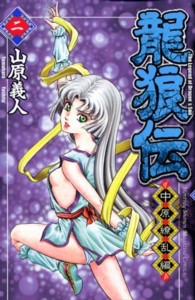目次
1 学習指導改善の視点(協同学習がめざす学力;教育観の転換を)
2 協同学習の理解(グループ学習が協同学習ではない;協同と競争の意味 ほか)
3 さまざまな協同学習(日本の協同学習;外国の協同学習 ほか)
4 学び合いを促す51の工夫(導入の工夫;展開の工夫 ほか)
著者等紹介
杉江修治[スギエシュウジ]
1948年生。中京大学国際教養学部教授。博士(教育心理学)。日本協同教育学会理事、日本教育心理学会・日本心理学会・日本グループ・ダイナミックス学会・日本教師教育学会会員、他(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆうり
3
正しく効果のある協同学習を実践的に説明してくれて、とても学びになった。協同学習だと思って受けてきたものが、全然効果をもたらしていない形式的なものであることに気づいた。51の項目もただ肯定的に受け取るのではなく、批判的な目線も持ち実際に想像することで、より深く理解することができた。2023/09/20
epitaph3
3
2015年240冊目。なかなか通読するには苦労する。確かに51の工夫は便利だが、その工夫の意図するところを、そして協同学習の目的を理解する必要がある。僕にはなかなか頭にはいらない文章だったが、協同学習入門としては、かなりまとまっている本だと思う。2015/05/08
みこと
2
協同学習についてたくさん知ることができた。協同学習とはと聞かれると何かわかっていなかったが、グループ学習が協同学習なわけでもないと覚えた。後半は教員として生かしていきたいと思う実践的なことばかりだった。2024/08/28
松島凜佳
2
協同学習の本当の意味について学ぶことができると思った。ただグループを作ることが協同ではないことや、グループの人数の意味なども知ることができる。2023/08/29
井手です
2
教壇に立った際に実践できる内容が書いてあった。 普通に生活する上では気付けない杉江さんの実体験を通してのアドバイスがたくさんあったのでタメになった。2021/02/09
-

- 電子書籍
- 赤ちゃんポストの真実