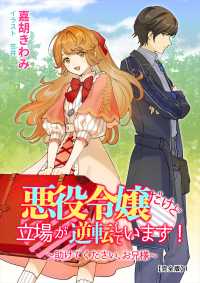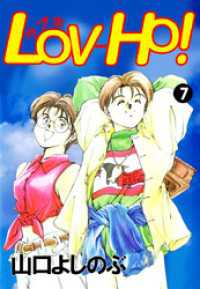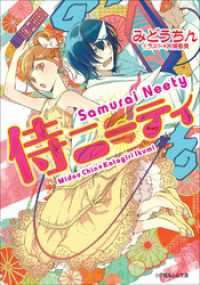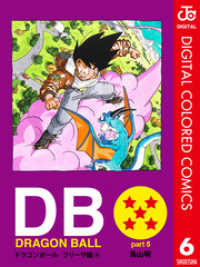内容説明
欧米人の鯨観の謎に迫り、その恣意性を暴く。誰が何の目的で鯨を神聖視し特別扱いし、メディアがどのように表象してきたか―その過程を徹底的に解き明かす。
目次
第1章 鯨の自然史、捕鯨の歴史
第2章 動物保護運動と鯨
第3章 捕鯨問題の政治性
第4章 抗議ビジネスとしての環境保護
第5章 メディアと鯨
第6章 捕鯨文化と世界観
著者等紹介
河島基弘[カワシマモトヒロ]
1965年静岡県に生まれる。1988年早稲田大学政治経済学部卒業。時事通信社入社。(記者職)。1998年時事通信社退職。エセックス大学社会学部修士課程修了。1999年ロンドン大学経済政治学院(LSE)社会人類学部修士課程修了。2004年エセックス大学社会学部博士課程修了。(PhD in Sociology)。現在、群馬大学専任講師。(専攻/文化社会学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろただでござる
0
どれだけ事実を並べてみても認めたくないと感情的になっている人を説得する事はできない。その類いの人たちには現実という物が存在しないんだろう。2013/07/31
はるこ
0
捕鯨に関して中立的に考察しているとは思えないが興味深い話がいっぱい。人が捕鯨問題に関して感情的になりやすいという一つの実例でもあるかな。本文じゃないけど羊とオーストラリア人のやり取りが面白かった。羊「メーーー」2013/01/28
tama_lion
0
よくある結論ありきの捕鯨擁護一辺倒な本だなーとしか2012/01/16
Rusty
0
欧米人が捕鯨に反対する理由を知りたくて読んだ。最も説得力を感じたのは、ピーターシンガーの『動物の解放』の内容。動物に道徳的配慮が必要かどうかは、その動物が痛みを感じる能力を持つかどうかによる。哺乳類や鳥類、魚や甲殻類には苦痛を示す兆候が見られるため配慮すべき。一方で、タコを除けば、貝類(牡蠣など)ほか軟体動物は発達した神経組織を持たないため、配慮は必要ない。 しかし、これらの思想を紹介した2章と、フリッパーやスタートレックに言及した5章以外は、副題の内容には関係ない反・反捕鯨の主張を並べたものだった。2019/03/03