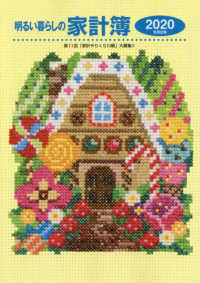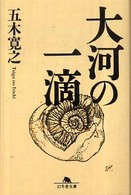目次
モバイルメディア:公衆電話が架橋した“声の文化”と“文字の文化”
テレビと動画:インターネットがテレビを乗り越えるまで
インターネット:大学生文化としてのWeb1.0
カメラ:小型化するカメラ、端末化するカメラ
ファッション:独自性の主張から共感的な同調へ
LGBT:可視化する性的マイノリティ
アート:美術館から日常へ
スポーツ観戦:グローバル化・ローカル化・物語化
夏フェス:コモディティ化とコミュニティ化
音楽:CDを売る時代から体験を売る時代へ
ゲーム「バーチャル」から「日常」へ
マンガ:媒体の変化と作品の多様化
書店:邪道書店の平成史
ショッピング:商業施設が媒介する文化の変容
外食:セルフサービスの空間と時間
著者等紹介
高野光平[コウノコウヘイ]
1972年生まれ。茨城大学人文社会科学部教授
加島卓[カシマタカシ]
1975年生まれ。筑波大学人文社会系教授
飯田豊[イイダユタカ]
1979年生まれ。立命館大学産業社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かやは
6
90年代のインターネットが無い時代と現代の歴史を比較する。モバイルメディア、テレビと動画、 インターネット、 カメラ、ファッション、 LGBT、 アート、スポーツ観戦、夏フェス、 音楽、 ゲーム、マンガ、書店、ショッピング、外食の15のテーマで語られる一冊。対象は大学生なのかな。ダイヤルQ2使いすぎて親に怒られてり、携帯電話でパケ死したことを思い出した。ウリナリはネットに毒されず純粋に見ていたなあ。高校生の頃にデジカメをもらって「ザの人」に写真を載せたことをきっかけに現在、写真関係の仕事についている。2024/05/11
ぷほは
2
2018年の初版は1メディア編、2趣味編、3現場編という構成だったが、新版は順序が入れ替えられて部ごとのまとまりが多少ずらされ「社会運動」が「LGBT」に置きかえられた。現Xはツイッターの呼称で統一されているが、各執筆者でコロナ禍への距離感は異なり、追加情報を多く書く人もいれば少な目の人もいる。学生と親世代の対話のきっかけとなった初版のリアクションをフィードバックしつつ、ニューノーマルな現代文化を捉えるための準備運動が始まっている。講義シラバスの参考図書リストに、岩波講座『文化・メディア』と共に書かねば。2023/12/31
reg_anjet
0
第一印象で教科書というよりは学生の卒論みたいだと思ったけれども、各章の展開が極めて似通っていることを踏まえると、おそらく意図的に「卒論の模範解答」的なスタイルで足並みを揃える編集方針なのだろう(※書名の副題で分析対象を統一している)。社会学的な考察に特有の面白さを提示する一歩か二歩ほど手前で論考が終わっている章も幾つかあり、正直に言えば教科書としても消化不良気味に感じる。全15章あって対象が幅広く、それぞれで現在と過去を網羅しているので、「大衆文化」を学ぶにあたっての関心のフックが非常に多いのは長所。2024/09/23