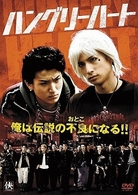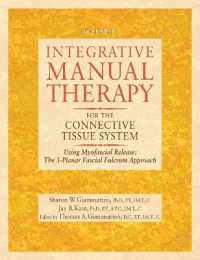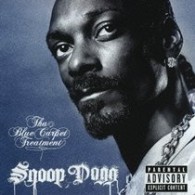出版社内容情報
あなたには師匠はいますか?
先般、師弟間でパワハラ問題が発生。弟子の「告発」によって落語界に大きな一石が投げ込まれた。仲間内ではだんまりか弟子への擁護の声が大きい。悪く言う人は仲間内にはいない。一方ネットの反応は「司直(民事・刑事)に訴えることはない」「伝統芸能の世界では師匠は絶対だ。師匠が白いものでも黒と言えば黒になる」「芸人のルールと世間の常識や法律は別」という声も多い。しかし一般人がなぜ「芸人のルール」などと言えるのか。さらには「伝統」というが、伝統というのは室町時代から続く能・狂言の側が言うのはわかるが、落語や歌舞伎も江戸時代からはあるけれど、今のルールが確立したのは「戦後」なのだ。落語界に暴力はあるのか。果たして師匠の言うことは絶対か。喫緊の問題を斬る!
内容説明
あなたには師匠はいますか?「パワハラ問題」発生。弟子の「告発」により落語界に大きな一石が投じられた。ここに書いたことが正しいなんて思ってはいない。結論もきちんと書いたわけではない。ただ本書が議論のきっかけになればいいと思う。
目次
第1章 落語家の師弟とは何か?
第2章 師弟関係から見た落語の歴史
第3章 ハラスメントと落語
第4章 修業とハラスメント
第5章 元・天歌の件の動向
番外 師匠と私
著者等紹介
稲田和浩[イナダカズヒロ]
東京都出身。作家、演芸作家(浪曲・落語・講談・漫才の台本、新内・長唄・琵琶・その他現代邦楽の作詞、演劇の脚本、演出)、演芸評論家など。日本脚本家連盟演芸部副部長(2023年3月現在)、文京学院大学外国語学部非常勤講師(日本文化論、芸術学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fwhd8325
道楽モン
qoop
funkypunkyempty
tarorhythm3