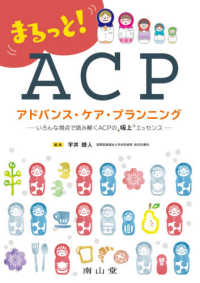出版社内容情報
江戸・明治時代を舞台にして古典落語を擬した新作落語である「擬古典」。
その擬古典の具体的なつくり方を中心に、擬古典とはいったいどういうものか、
いまなぜそれを取り上げるのか、を論じ、また現在、高座に掛けられている
擬古典の名作の紹介や執筆に役立つ書籍も提示、そのほか、落語作家としての
心構え、そもそも「落語作家は食えるのかどうか」という究極の問いへの答えまで
……著者がこれまで発表してきた落語の解説と速記とともに語りつくす。
本書に登場する主な落語家さんは、立川談四楼、柳家一琴、立川談慶、柳家小せん、
柳家小傳次、林家たけ平、春風亭三朝、桂夏丸、立川こはる、入船亭小辰、立川寸志、
雷門音助、立川だん子(敬称略)。
落語家さん、天狗連の方、落語会主催者の方、新作派はもちろん古典派の落語家さん、
ファンの方も本書に興味がある人は多いはず。乞うご高覧ください!
[目次]
(第1章)落語の作り方・落語作家の心構え・擬古典とは何か。
(第2章)井上作の落語のあらすじとサゲ、そのクスグリとポイントを解説。
(第3章)井上の擬古典が口演された際の速記および加筆・修正したもの。
内容説明
江戸期・明治期を舞台として古典を擬した擬古典落語。その具体的なつくり方を中心に、擬古典とはどういうものか、なぜいまそれを取り上げるのか、また高座にかけられている擬古典の名作、そして落語作家の心構え、さらには「落語作家は食えるのか」という究極の問いへの回答等、これまで発表してきた落語をはじめ、懇切丁寧に解説する。
目次
第1章 おぼえがき二十篇(擬古典ものを古典派のために;あてがきは敬意のあらわれ;初稿はつまらないのが当たり前 ほか)
第2章 全二十六席のかんどころ(「殿様いらず」春風亭三朝師匠;「わけあり長屋」林家たけ平師匠;「みちばた詩人」桂夏丸師匠 ほか)
第3章 おしゃべり四席(「正体見たり」立川寸志さん;「赤猫」林家たけ平師匠;「御落胤」柳家小せん師匠 ほか)
著者等紹介
井上新五郎正隆[イノウエシンゴロウマサタカ]
1975年新潟県三条市出身。1998年二松学舎大学文学部国文学科卒業。2002年から「ドージン落語(コミックマーケットに参加するような、いわゆるアキバ系と呼ばれる人たちの物語を一席の落語にしたもの)」を発表、13年かけて98席執筆。2016年から「落語作家」の看板を掲げ、擬古典ものの新作落語を中心に落語家たちにあてがきをして、2002年3月現在、総勢13人に26席が実際に口演された(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ねこまたとあさごはん 分冊版18
-

- 電子書籍
- プレジデント Family 2020年…