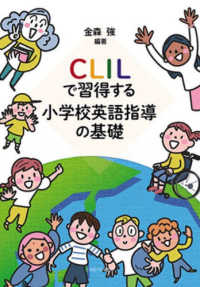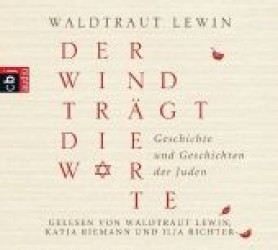出版社内容情報
19世紀末から20世紀半ばの日本、そして世界は、
まさに激動の時代であり、その時代を生きた
近代の「知識人」たちは刻々と変わりゆく世界情勢を
どのように視ていたのか?
本書の探求は、2017年の現在もその時々の国際情勢の
「現実」をどのように見据えるのか、
いかにして自分たちの立ち位置を定め、かつ「外」と
向き合うかという「現代日本の対外認識」に関する
多くの手掛かりを与えてくれる。
【目次+執筆者】
総 論
「転換期の国際社会」を知識人たちはどう捉えたのか
(萩原稔・伊藤信哉)
第1章
五・四運動以後の日本知識人の中国認識
――矢野仁一と内藤湖南(萩原稔)
第2章
大村欣一東亜同文書院教授の中国認識
――1910?20年代の研究とその特徴(武井義和
=愛知大学東亜同文書院大学記念センター研究員、愛知大学非常勤講師)
第3章
近代日本における「文化主義」の登場とその展開
――桑木厳翼・金子筑水・土田杏村(大木康充
=大東文化大学非常勤講師)
第4章
国際問題評論家の対外認識
――稲原勝治と米田実(伊藤信哉)
第5章
再生産されるモンゴル認識
――善隣協会調査部と戦時下のモンゴル研究
(鈴木仁麗=明治大学、早稲田大学非常勤講師)
第6章
清沢洌の国際水平運動
――〈植民地・社会主義〉の視角から
(上田美和=早稲田大学非常勤講師)
第7章
戦前・戦中・戦後直後娯楽番組の連続性と政治性
――丸山鐵雄の番組制作と大衆芸能論を素材として
(尾原宏之=立教大学非常勤講師)
第8章
外務省と日本の国連加盟外交――米ソ冷戦の狭間で
(種稲秀司=國學院大學文学部兼任講師)
第9章
海上自衛隊の創設における旧海軍軍人の対外認識
(畑野勇=株式会社古藤事務所勤務)
第10章
「改憲派」の再軍備論と「日米同盟」論
―徳富蘇峰・矢部貞治・中曽根康弘
(小宮一夫=駒沢大学非常勤講師)
萩原 稔[ハギハラ ミノル]
はぎはら・みのる
大東文化大学法学部准教授。
1974年生まれ。
同志社大学大学院法学研究科博士課程修了、
博士(政治学)。専攻:日本政治思想史。
著書『北一輝の「革命」と「アジア」』
(ミネルヴァ書房、2011年)、
編著書
『大正・昭和期の日本政治と国際秩序』
(思文閣出版、2014年)、
『北一輝自筆修正版 国体論及び純正社会主義』
(ミネルヴァ書房、2008年)の編集にも関わる。
伊藤 信哉[イトウ シンヤ]
いとう・しんや
松山大学法学部准教授。
1969年生まれ。
早稲田大学大学院政治学研究科博士課程単位取得退学。
専攻:日本政治外交史。
主著『近代日本の外交論壇と外交史学
――戦前期の『外交時報』と外交史教育』
(日本経済評論社、2011年)、
『外交時報総目次・執筆者索引―戦前編』
(日本図書センター、2008年)。
内容説明
19世紀末から20世紀半ばの日本、そして世界はまさに激動の時代であった!刻々と変わりゆく世界情勢に対するその時代を生きた近代の「知識人」たちの視座を再認識することによって、その時々の国際情勢の「現実」をどのように見据えるのか、いかにして自分たちの立ち位置を定め、かつ「外」と向き合うかという「現代日本の対外認識」に関する多くの手掛かりを得られるに違いない。
目次
総論 「転換期の国際社会」を知識人たちはどう論じたのか
第1章 五・四運動以後の日本知識人の中国認識―矢野仁一と内藤湖南
第2章 大村欣一東亜同文書院教授の中国認識―一九一〇~二〇年代の研究とその特徴
第3章 近代日本における「文化主義」の登場とその展開―桑木厳翼・金子筑水・土田杏村
第4章 国際問題評論家の対外認識―稲原勝治と米田実
第5章 再生産されるモンゴル認識―善隣協会調査部と戦時下のモンゴル研究
第6章 清沢洌の国際平水運動―“植民地・社会主義”の視角から
第7章 戦前・戦中・戦後直後娯楽番組の連続性と政治性―丸山鐵雄の番組制作と大衆芸能論を素材として
第8章 外務省と日本の国連加盟外交―米ソ冷戦の狭間で
第9章 海上自衛隊の創設における旧海軍軍人の動向と対外認識
第10章 「改憲派」の再軍備論と「日米同盟」論―徳富蘇峰・矢部貞治・中曽根康弘
著者等紹介
萩原稔[ハギハラミノル]
1974年生まれ。同志社大学大学院法学研究科博士課程修了、博士(政治学)。現在、大東文化大学法学部政治学科准教授
伊藤信哉[イトウシンヤ]
1969年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程単位取得退学。現在、松山大学法学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。