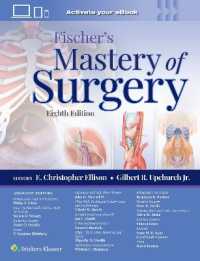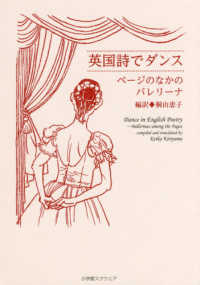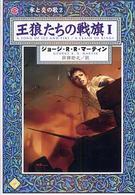- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
なぜ湖北地方(滋賀県北東部)には優れた観音像が多く残っているのか──「観音の里」の形成を検討し、湖北の精神風土の特質を探る。なぜ湖北地方(滋賀県北東部)には
優れた観音像が多く残っているのか
「観音の里」はどのように形成されたのか、
渡来人による大陸の先進文化、古代氏族による在来信仰、
式内社と古墳に対する信仰、
伊吹山・己高山を中心とした仏教文化や山岳信仰、中世以降の仏像の奉祀、
そして現在も湖北に残る、春を告げる行事「オコナイ」等から検討し、
湖北の精神風土の特質を探る。
?湖北地方(旧伊香郡・浅井郡・坂田郡)には、
長浜市高月町向源寺(渡岸寺観音堂)の十一面観音立像【国宝】や
木之本町石道寺の十一面観音立像【重要文化財】をはじめ、
平安時代初期以降の多くの優美な観音像が祀られている。
とくに高月町は「観音の里」と呼ばれ、白洲正子の随筆や
井上靖の小説『星と祭』で広く知られている。
?目次内容?
第一章 天日槍と渡来人
一 湖北の黎明期
二 天日槍
三 湖北における天日槍
第二章 湖北の古代氏族と信仰世界
一 湖北の古代氏族
二 古代氏族と式内社
三 式内社と古墳
四 自然崇拝
第三章 仏教文化と山岳宗教
一 仏教伝来
二 古墳から寺院へ
三 山岳信仰(一):伊吹山
四 山岳信仰(二):己高山
第四章 「観音の里」の成り立ち
一 山を下りた仏像たち
二 村人に守られる仏たち
三 村の成り立ち
四 霊場巡り
第五章 湖北のオコナイ
一 オコナイの源流
二 オコナイの特質
三 オコナイにおける神と仏
大東 俊一[ダイトウ シュンイチ]
だいとう・しゅんいち
人間総合科学大学大学院教授。専門:比較思想・比較文学、日本思想史。
【著書】
『ラフカディオ・ハーンの思想と文学』(彩流社、2004)、
『日本人の他界観の構造』(彩流社、2009)、
『日本人の聖地のかたち──熊野・京都・東北』(彩流社、2014)ほか。
内容説明
「観音の里」はどのように形成されたのか―渡来人がもたらした大陸の先進文化、古代氏族による在来信仰、式内社と古墳に対する信仰、伊吹山・己高山を中心とした仏教文化や山岳宗教、中世以降の惣村での仏像の奉祀、そして現在も湖北に残る、春を告げる行事「オコナイ」等、湖北の歴史から掘り起こして検討する。
目次
第1章 天日槍と渡来人(湖北の黎明期;天日槍;湖北における天日槍)
第2章 湖北の古代氏族と信仰世界(湖北の古代氏族;古代氏族と式内社;式内社と古墳;自然崇拝)
第3章 仏教文化と山岳宗教(仏教伝来;古墳から寺院へ;山岳信仰(一)伊吹山
山岳信仰(二)己高山)
第4章 「観音の里」の成り立ち(山を下りた仏像たち;村人に守られる仏たち;村の成り立ち;霊場巡り)
第5章 湖北のオコナイ(オコナイの源流;オコナイの特質;オコナイのける神と仏)
著者等紹介
大東俊一[ダイトウシュンイチ]
1954年、岐阜市生まれ。1978年、東京外国語大学外国語学部フランス語学科卒業、1980年、東京外国語大学大学院地域研究研究科地域研究専攻修士課程修了、1986年、法政大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士後期課程単位取得満期退学。人間総合科学大学開学時の2000年に専任講師として着任、2004年より同大学大学院人間総合科学研究科教授、2016年6月、死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
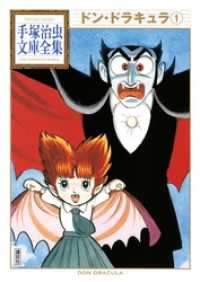
- 電子書籍
- ドン・ドラキュラ 手塚治虫文庫全集(1)