内容説明
パレスチナで何が起こったのか…。
目次
1 子どもたちは見た(少女マリアム;家族すべてを失ったアミーラ;母の白旗 ほか)
2 サムニ家の子どもたち(ガザ市の中では最も大きな町;三歳のムハンマドも見た;薬莢を集めるカナアーン ほか)
3 子どもたちは今(悲しみに耐えるゼイナブ;ポーランドに招待されたモナ;大人たちが語る子どもの心の傷 ほか)
著者等紹介
古居みずえ[フルイミズエ]
1948年島根県生まれ。アジアプレス所属。JVJA会員。1988年よりイスラエル占領地を訪れ、パレスチナ人による抵抗運動・インティファーダを取材。パレスチナの人々、特に女性や子どもたちに焦点をあて、取材活動を続けている。98年からはインドネシアのアチェ自治州、2000年にはタリバン政権下のアフガニスタンを訪れ、イスラム圏の女性たちや、アフリカの子どもたちの現状を取材。新聞、雑誌、テレビ(NHK総合・ETV特集・NHKBS1、テレビ朝日・ニュース・ステーション)などで発表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
179
世界の事柄を拾い上げると、悲しみと喜び、どちらが重いのだろう。人間は生い立ちのなかで心が形成される。一方が善で悪ということはない。うつろな眼差しは互いに涙をためている。もし今ここで何かが起これば、綺麗事は消え去り心身は崩れ去るだろう。憎しみも悲しみもどこに隠すのだろう。時を経てもそこに鍵をかけたことは忘れない。閉じ込めた記憶は薄れても、開ければそこにある。一人ひとりの体験を記す本書の中だけでも何人が亡くなったのか。恐怖と悲しみにいつも泣いている。取材から15年、あの頃の子どもたちは今、心の中で叫んでいる。2023/10/22
まさ
21
読み友さんのレビューから知った1冊です。発刊は2011年。いまの侵攻を記しているのではない。それぞれが受けた酷いできごとに読み進めることを止めてしまうばかりだった。そして、10年以上も苛まれ背負ってきたいまがある。ガザで起きてきたこと、いま起きていることを世界中が直視しないと。2023/10/24
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
12
聞き飽きたかと思いますが、ノンフィクションはその素材について語るのではなくて、いかに書かれているかについてフォーカスするべし、と思っておりますが、素材がすさまじかったのか、料理の仕方がすごかったのか、もうどうでもよくなった。お腹いっぱい。すべてを失った人々に残ったのはイスラム教だけ。しかしその教えも彼らを救わない。親を失った子たちが繰り返し言葉にするのは「イスラエルが何をしたのか知ってほしい」、そしてそれを知った人はどうするべきか。生き残った子らはほとんどが人を救いたい、と言う。救えなかったゆえに。2017/07/27
けんとまん1007
9
この事実を世界は知らない。いや、知らないふりをしようとしているのだと、著者は訴えている。過去、いろいろとあったイスラエルと周辺。それはそれとして、ここで語られていることは、絶対に許すことができない。降伏の白旗を持っている人たち、子どもたちに対して平気で銃をこれでもかと向けて撃つイスラエル軍。家にもどれば、こころやさしい父親かもしれない人が、いとも簡単にそうなってしまうという事実。赤十字をも止め、銃を向けるということは、いったい何を意味するのだろうか?今の時代は、一人一人のメデイアを観る目が大事だ。2011/10/03
Erika
6
イスラエル軍によるガザ地区への攻撃が凄惨過ぎて、言葉も出ない。農業を営む穏やかな家族を襲った悲劇。白旗を揚げ武装もしていない民間人を狙うなんて卑怯極まりない。家族や親戚が100人位1つの家に閉じ込められ、外から集中砲撃された話は衝撃的だった。生き残った子供達は今も悪夢にうなされ、「何故?私達が一体何をしたの?」と問いかけ続けている。イスラエルとパレスチナに和平は訪れるのだろうか。2020/11/18
-
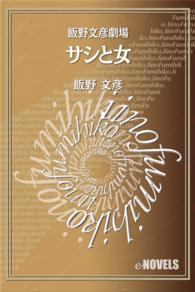
- 電子書籍
- 飯野文彦劇場 サシと女


![ビーグルカレンダー 〈2025〉 [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44169/4416924607.jpg)




