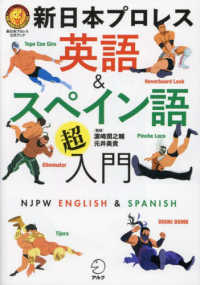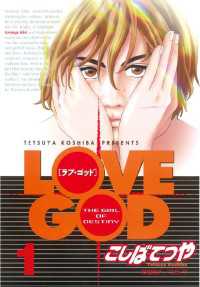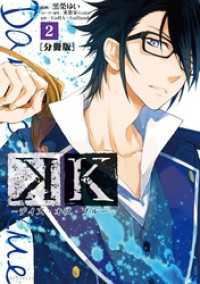- ホーム
- > 和書
- > エンターテイメント
- > TV映画タレント・ミュージシャン
- > エンタメカタログ
出版社内容情報
日本のヒップホップが沸騰した伝説の90年代を、17人の“証言"で振り返る!
リアルサウンド編集部[リアルサウンドヘンシュウブ]
内容説明
日本のヒップホップが沸騰した伝説の90年代を、17の“証言”で振り返る。
目次
1 90年代ジャパニーズ・ヒップホップシーンの創造(YOU THE ROCK★―90年代ヒップホップの着火点;K DUB SHINE×DJ MASTERKEY―アメリカから持ち帰ったヒップホップ精神;宇多丸(ライムスター)―日本語ラップの進化と“B‐BOYイズム”の確立
川辺ヒロシ―LB系の“空気”を生んだ横のつながり
DABO×サイプレス上野―ヘッズから見た、90年代ヒップホップシーンの輝き)
2 カルチャーとしてのジャパニーズ・ヒップホップ(CRAZY‐A―元祖B‐BOYが語る、4大要素の発展と分化;DJ KENSEI×DJ YAS―DJの視点から見たヒップホップシーンの変遷;DJ YANATAKE―宇田川町が“レコードの聖地”だった頃;KAZZROCK―ヒップホップとグラフィティの交差点)
3 ヒップホップ・カルチャーの伝播(BROOKLYN YAS―日本でヒップホップをビジネスにした男;高橋芳朗×古川耕―ヒップホップ専門誌『FRONT』『blast』が担った役割;加倉井純―オーガナイザーが見た、当時のクラブシーン;森田太(TOKYO FM)―『ヒップホップナイトフライト』から次世代へ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
showgunn
17
80年生まれの自分は90年代がまるまる10代の10年と重なるわけで、まさに思春期の真っ最中に熱狂した日本語ラップについての本、ということであっという間に読み終わった。知ってる話も多いからあっという間に読めたけど、入り口としてはそんなにわかりやすくはないかもしれない。そこらへん、客観的にどうなのかは自分にはわからない。一番面白かったのは日本語ラップシーンのど真ん中にいたとは言えない川辺ヒロシのインタビューで、シーン全体についてというより、個人的にあの時代をどう過ごしたか、という話の方が興味ある。2017/01/27
チネモリ
8
Japanese hip hopを追いかけた10代。情報が本当に少なく手探りで音源を聴き漁った。同様に当事者たちも試行錯誤し切磋琢磨しながら今日のシーンを築き上げてきた。90年代を代表する当事者たちの「証言」から浮かび上がるのは「教科書がなかったこと」である。だからこそ様々なことに挑戦し独自のhip hop文化を根付かせることができた。最近「フリースタイル・バトル」が浸透してきている。日本のhip hop形態がまた変化してきている。それでも結局”Hip hop will never die”である。 2018/06/26
nizimasu
8
うむむ、懐かしい。個人的にはLBなんかは渋谷系の文脈。それ以前のラップはクラブミュージックの誕生で日本ではメジャーではAVEXとかアルファとかがコンピ出したりしていたのを聞いていたので特に初期のストーリーは懐かしい。ブッダとかシャカゾンビまでが自分のリアルタイムと重なる部分。それ以外も最近の「フリースタイルダンジョン」のおかげで随分注目されていてそれがまたいいのだな。大著ではあるけどやっぱりまだまだヒップホップというか90年代の音楽シーンは渋谷系含め乱れ咲きの最後の時代だったなあと痛感する。2017/02/13
雛坂 五里霧中
5
★★☆☆☆ 複数人へのインタビュー形式。誰もが同じ内容で話すので途中ダレる。DJ KENSEIとニトロのワードが溢れすぎてつらい 笑 巻末のオススメCD集は良かった。2020/03/04
Masaaki Kawai
4
Rの本を読んで、そういえば途中までやったと読み終えました。音楽からダンス、グラフティの4要素からオーガナイザーなど幅広く取り上げられ、リアルタイムで経験したもんじゃないので、どちらかというと歴史の感覚で。たびたび出てきた、あの時代はネットがないから現場に行かんとというのが、バイタリティに繋がったのかなーと。2019/11/21