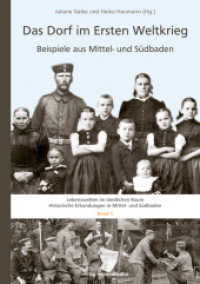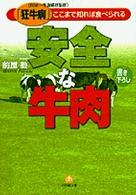目次
2 並ロの形式別解説(上巻からの続き)(オロ36;オロ40 ほか)
3 軍用客車の時代
4 近代化改造と蛍光灯化
5 その後の改造、廃車(格下げと通勤形改造;寝台車への改造 ほか)
6 北海道の並ロ運用と編成記録
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えすてい
6
現在では1〜2両の気動車列車が1日何本あるのかという路線ですら、この本が取り上げた時代には旅客車だけで5両程度組成され、そのうち最低でも1両はロまたはロハが連結されていた。幹線のロからからローカル線のハへののりかえはあまりに落差が大きすぎてロやロハが必要だったのだろう。北海道の普通列車も、今では考えられない行先の長距離鈍行列車がロやロハを連結し道内を日々あちこち行き来して忙しい運用に就いていた。ところで本州からの転属車は北海道用に二重窓に改造されるのだが、二重窓への改造はそんなに簡単にできるのだろうか?2023/10/16
えすてい
5
並ロがロとしての役目を終えると、廃車にならなかったものは、ただでさえ並ロは改造車も多々あったが、再改造を受けて、クロスシートを撤去して吊り革付きロングシートになったり(これは容易に電車を増やせなかった仙台地区のラッシュ対策が主)、荷物車マニ36になったりしたものもある。一方で、事業用車への改造は少なく、旧型客車改造の鉄板である救援車への改造も微々たるものしかないようだ。配給車へは写真すら入手できず。また、並ロは戦後は占領軍への接収もあり、占領軍人の体格の問題から前列のない「ロニ」なるものも登場したと。2023/10/10
-
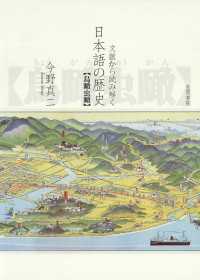
- 電子書籍
- 文献から読み解く日本語の歴史