内容説明
絶対的な権力に対して歌人は何ができたのか、迎合するのみであったのか―権力への抵抗、苦闘の軌跡を戦時詠から見直し再考する!時流に翻弄されながらも、ひそかに己の矜持を守り詠った二十余名の歌人論を中心に、学徒出陣の歌、戦地詠、抑留詠などを採りあげ、昭和十年代の歌壇の実像をも描出する迫真の集大成。
目次
第1部 苦闘した戦時詠の遺産(国民詩人の北原白秋;現地詠を開いた渡辺直己 ほか)
第2部 過酷な学徒出陣と勤労動員(まず教師が立ち上がる;早稲田大学の場合 ほか)
第3部 弾圧された運動体(戦後に発表された獄中詠;内田穣吉と布施杜生 ほか)
第4部 迷路に入り込む歌壇(二・二六事件の衝撃;表現の自由の抑圧 ほか)
著者等紹介
篠弘[シノヒロシ]
1933(昭8)年、東京生まれ。小石川高校を卒え、51年に早稲田大学入学とともに、歌誌「まひる野」に入会、土岐善麿、窪田章一郎に師事、目下その代表。55年に小学館に入社、百科事典・辞典をはじめ一般書籍を企画し、取締役出版本部長を担い、98年まで社長室顧問。在社中から現代短歌の論作に従事し、現代歌人協会理事長、日本現代詩歌文学館長、愛知淑徳大学文化創造学部長、日本文藝家協会理事長を経て、目下その常任理事。四〇年間つづけた「文芸選評・短歌」講師に対し、2014年にNHK放送文化賞を授与。歌会始選者、毎日歌壇選者などをつづける。主な歌集は、第一歌集『昨日の絵』(’84・5)所収「花の渦」で、80年に短歌研究賞。第四歌集『至福の旅びと』により、95年に迢空賞。99年に紫綬褒章。第五歌集『凱旋門』により、2000年に詩歌文学館賞。05年に旭日小綬章。07年に『篠弘全歌集』ならびに第七歌集『緑の斜面により、毎日芸術賞など。主な歌書は、『近代短歌論争史』全2巻(角川書店刊)、「明治大正編」(’76・10)、「昭和編」(’81・7)で、82年に現代短歌大賞。『自然主義と近代短歌』(’85・11、明治書院刊)などにより、92年に文学博士。『残すべき歌論―20世紀の短歌論』(2011・3、角川書店刊)は、12年に斎藤茂吉短歌文学賞を授与する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
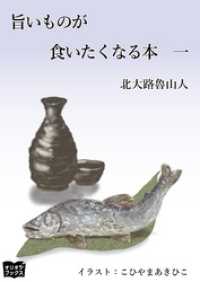
- 電子書籍
- 旨いものが食いたくなる本 一
-

- 和書
- アメリカ物語 〈続〉





