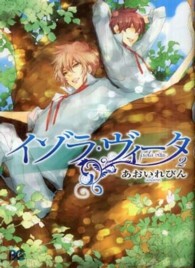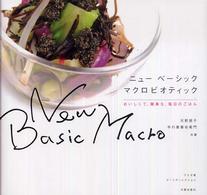内容説明
日本語に「マル抜け文」が多いのはなぜ?英語で学ぶと簡単なことが、日本語で学ぶと分かりにくくなるのはなぜ?なんとマルマル一冊「句読点」についての話です。ことのほか「文字」に関わることの多い方、必読の書!!
目次
私たちの総合判断
第1部 テンとマルの現在地(子供たちが見るテンとマル;国語のテンとマル;算数・数学のテンとマル)
第2部 日本語表現の現在地(プロンプトとしての日本語表現;横書き教科書の日本語プロンプト)
私たちの現在地
テンとマルの等価変換
付録
著者等紹介
芝原宏治[シバハラコウジ]
福井県武生市生まれ。東京教育大学文学部卒、東北大学大学院文学研究科博士課程中退、大阪市立大学博士(文学)、大阪市立大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
34
文章を書いていて、テンとマルの打ち方に困った覚えがだれにでもあるだろう。しかし本書はそれを指導する本ではない。冒頭部分で、引用がある文の場合には、句読点の打ち方を正則に沿って行うと、奇妙に見苦しい文ができあがることを述べ、句読点の使い方に警告を発している。中盤からは、文章表記そのものが、意味を表すのではなく、意味を想起するように促すものだと論じる。文の意味を取りにくい場合、それは読者の責任ではないことを「プロンプト」という言葉を使って述べている。句読点について、深く分析した鋭い本である。2014/12/11
ブルーローズ
4
2013年12月31日読了。かるーく見過ごされがちですが、言語運用上、結構大事な句読点。「ここではきものをおぬぎください」のどこに入れるか?だけじゃない。かなり広い分野にわたっているので、雑学に、疑問解消に、授業用にぜひご活用ください。寝る前にはオススメしませんww2014/01/25
のりたま
1
テンとマルだけでなくナカテンや「」等の符号、字下げなどの体裁もカバーする内容。日本語のテンとマルの使い方については本書の附録にもある「句切り符号の使ひ方〔句読法〕(案)」が知られている。これに基づく教科書を「国語式」とし、「新聞式」との違いについて例を挙げて説明。学習指導要領が独特な句読点の使い方をしていることにも触れる。プロンプトの話で2章割き、英語の例も詳しい。添え仮名のある漢文の引用の用例については、解説が簡単すぎるからか納得できない点あり。200頁「古来より」は誤用というより文選読み的な印象。2022/03/06
栗きんとん
1
あ〜おもしろかった。くどい、くどい。算数と数学が難しいのは、日本語のせいだったのね。2013/07/31
-

- 和書
- 近代中国絵画