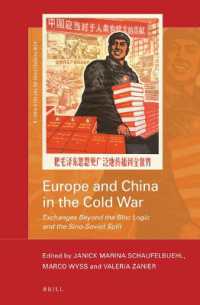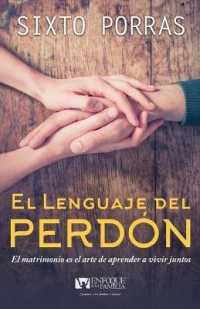出版社内容情報
日本のスーパーで売られている食品がどこで生産されて、どこから来ているのか、その詳細を知れば、いかに日本の食卓は外国産のもので溢れかえっているのかがわかります。日本の食料自給率は1960年代後半から年々低くなっており世界でも最低レベルです。日本は国土の7割が森林で農産物の生産量が増やせないといった事情がありますが、食料不足に対する不安をなくすために何ができるのか、そんな問題意識を持っていただけたらと思っています。
目次
1 スーパーマーケットにならぶ食品はどこからきている?(スーパーマーケットに行ってみよう!;食品の売り場をみてみると…;どんなところからきているの?;これ、ぜーんぶ外国産!;日本への輸入が多い国は? ほか)
2 日本の食料自給率ってどのくらい?(外国産の食料がなかったらどうなる?;日本人の食事の変化;日本の食料自給率はどのくらい?;世界の食料自給率はどうなっている?;食料自給率はこのままでいいの? ほか)
著者等紹介
梅澤真一[ウメザワシンイチ]
筑波大学附属小学校教諭。専門は小学校社会科教育。日本社会科教育学会、全国社会科教育学会、日本地理教育学会などに所属。東京書籍『新しい社会』教科書編集委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
179
スーパーマーケットに並ぶ食材の不思議。夏野菜が冬に並び、冬野菜が夏に並ぶ。どこの食材なのだろう。誰が作ったのだろう。いろんな疑問が浮かんでくる。食料自給率は低いはずなのに、食べたいものをいつでも得られる日本。海外でトラブルが起きれば、燃料や飼料価格が上昇し、そんな贅沢も難しくなる。食品ロスを減らし、食への感謝を忘れてはいけない。旬の食材をいただき、できる限り地産地消を心掛けたい。栄養価の高い食材を、安全な食品を、食料の持続性を。世界情勢が目まぐるしく変化するなかでも、世界中の人々に食が行き渡りますように。2025/01/22
どぶねずみ
24
小学校の先生が書いた本。地図帳の後ろに掲載されているような統計もあり、小学生には良書だと思う。前半はスーパーに並んでいる商品はどこから流通されてくるのか。産地や旬の時期などは私の社内試験で覚えさせられる内容だ。後半は日本の自給率の低さについての問題定義。自給率を上げるにはどうすればよいか、これはかなり長期化したテーマだ。50年先の自給率は上がっているだろうか。2025/03/02
ひつまぶし
3
読まなくても大体内容が分かる。よくできてるなと思った。食料自給率を考える時に、カロリーベースと生産額ベース、ふた通りの計算方法がある。食肉の自給率にしても、単純に生産額だけで計算する場合と、育てるための飼料が外国産であることを考慮した場合とでは全然違う。食料自給率を上げればいいのかというと、輸出を主要産業にしている発展途上国もあるだろうし、単純にそうとも言えないことは読んでいるうちに気がつくが、そうして気になるであろう論点まで終わりの方ではきちんとフォローしているからすばらしい。自分なりの比較にも便利。2025/03/14
キツツキ
1
スーパーマーケットのバックヤードの話の本かと思いましたが、違いました(よく見ない母が悪い)内容は小学校高学年向きかな。まさに副題の「食品はどこからくるの?」という話がメイン。トウモロコシ🌽の加工品やエビの養殖の仕方など私が読んでフムフム言ってました。2025/11/25