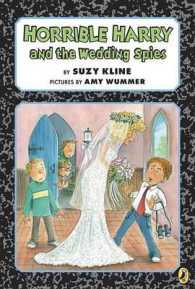目次
2011
2012
2013
2014
著者等紹介
森敏[モリサトシ]
1941年生まれ。1966年東京大学農学部農芸化学科修士課程修了。東京大学助手、助教授、教授、大学評価学位授与機構教授を経て、東京大学名誉教授。農学博士。NPO法人WINEP(植物鉄栄養研究会)理事長。専門は植物栄養学。日本土壌肥料学会賞、日本農学賞、読売農学賞、日本学士院賞を受賞
加賀谷雅道[カガヤマサミチ]
1981年生まれ。早稲田大学理工学部卒業。フランスで写真を学び、2011年帰国。2012年6月から放射線像プロジェクトを開始。これまで国内で8回の展示、マレーシアOBSCURA国際写真展で招待作品として展示(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
319
写真家の加賀谷雅道氏が東大農学部名誉教授の森敏氏の協力を得て成し遂げた快挙。放射能は目には見えず、音も匂いもない。私たちがその線量や、それが及ぼす人体への影響を知りえるのはベクレルやシーベルトといった単位だけ。これでは素人にはとても実感できはしない。そこで、見えないものを可視化してやろうとしたのが、今回の試み。植物をはじめ、動物や道具類まで特殊な方法で、それらの放射線量を鮮やかに見せてくれる。これによれば、動植物はことごとく内部被曝していることが一目瞭然だ。濃いドットは空中を飛散していたもの。⇒2018/03/10
たまきら
25
読み友さんより。2015年出版。読んでいたら夫が覗き込み、外部被ばくと内部被ばくの違いがどのように写るかを説明したら奪い取るようにして見始めた。写真にははまだ調査は必要だけれどこういうデータが集積された…と事実が淡々と記述されている。わかりやすいがそれは表面だけのもので、私たちは実は何もわかっていない。これから私たち同じ時を歩む者たちが、自身の身体で知ることになる。その事実のみをまた突きつけられた気がする。そして、再稼働。もんじゅ廃炉。道はまだまだ続く。2018/03/19
Mao
5
2014年に品川で採取した土も放射能まみれ。 近くにいる生物でも、汚染度には大きな差がある。サンプルを調べたからといって全部安全とは言えないことがよくわかる。 どんな生活をするか、何を食べるかにより、人間の汚染度も変えることができる。 各々の意識がとても大切。2015/05/21
トモ
2
今も汚染が続いているということを再認識させられた。 個人的には他地域のサンプルもあると汚染の実態が一層分かりやすいかなと思った。2015/03/19
くらーく
1
写真だけ見ると、墨絵のようでもあり美しいと言うと誤解を招くかな。見えるようにすると言うのは、共通の理解を得る上でとても大切だと思う。そういう意味では、本書は素晴らしい。 ただ、受け取る側がきちんと受け取っているかは微妙。数値も表記しているけど、その数値を読み取って、どう判断するかまでは言っていないのではないか。品川の例なんかは、汚染しているとは言い切れない数値のcpm値のようですが。放射線は0にはならないし、普通に生活しているだけでも浴びているわけだし。まあ、いろいろともやもやするところだありますな。2016/03/18
-

- 電子書籍
- BiCYCLE CLUB 2015年1…
-
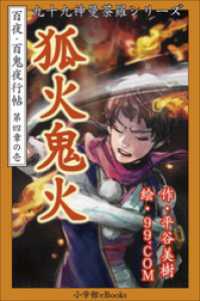
- 電子書籍
- 九十九神曼荼羅シリーズ 百夜・百鬼夜行…