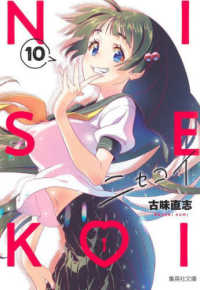- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
明治初期、日本のあるべき姿について熱く語り、独自の「憲法草案」を作り上げた若者たちがいた。
【著者紹介】
1925年、愛媛県生まれ。小・中学校での教員生活のかたわら、長年、読書運動をつづける。元・日本子どもの本研究会副会長。著書に『親子読書、このすばらしい出会いの世界』ほか。2014年2月、本書の推敲を終えたのち、病没。
内容説明
一九六八年八月二十七日。夏の日差しを浴びながら、曲がりくねった山道を進む、十数名の集団がありました。東京経済大学の色川大吉教授(当時)と、その教え子の大学生たちでした。やがて、一行の目の前に、古めかしい土蔵があらわれました。明治時代の初め、この地域の青年たちが、議論を重ねてつくりあげた憲法草案が、八十年余りもの長い眠りから、ついに目覚めるときが来たのです。「五日市憲法草案」をめぐる物語は、ここから始まります―。
目次
1 土蔵が開けられる(深沢家の土蔵;土蔵の二階は宝の山;千葉卓三郎とは、だれ?;新井さんの卒業論文)
2 放浪の人・千葉卓三郎(おいたち;新しい旅立ち)
3 卓三郎、五日市へ(山里の暮らし;教師となって;深沢親子;勧能学校の教室で;学芸講談会;女性の参加)
4 憲法草案づくりに燃えた五日市(自分たちの憲法をつくろう;将来の日本の姿;冬の夜;校庭の桜は満開;奈良橋村で;卓三郎が残したもの)
5 「五日市憲法草案」と「日本国憲法」(「五日市憲法草案」の特色;新しい日本への願い)
著者等紹介
伊藤始[イトウハジメ]
1925年、愛媛県西条市に生まれる。愛媛県師範学校(現・愛媛大学教育学部)、法政大学文学部卒業。40年間にわたり教員生活を送る。この間、1973年から親子読書活動にたずさわる。元・日本子どもの本研究会副会長。2014年2月病没
杉田秀子[スギタヒデコ]
1939年、福島県浅川町に生まれる。東京学芸大学卒業。東京都の稲城市・立川市の小学校教諭を勤める。児童文学創作グループ「ドラゴンの会」所属。日本子どもの本研究会会員
望月武人[モチズキタケヒト]
1937年、山梨県甲府市に生まれる。青山学院大学卒業。東京都区内・立川市内の小学校教諭を勤める。児童文学創作グループ「ドラゴンの会」所属。日本子どもの本研究会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モリー
seraphim
サラダボウル
moonanddai
ムーミンママ
-
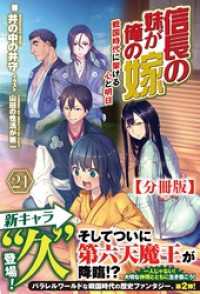
- 電子書籍
- 【分冊版】信長の妹が俺の嫁 21話(ノ…
-
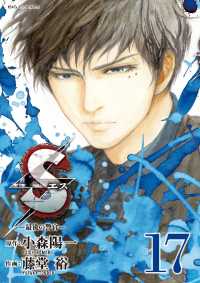
- 電子書籍
- Sエス―最後の警官―(17) ビッグコ…