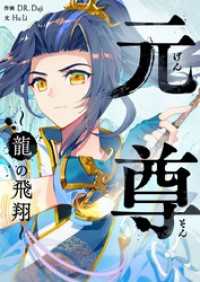出版社内容情報
古生物シリーズ第10弾は、『古第三紀・新第三紀・第四紀の生物 下巻』。長きにわたり世界に君臨した恐竜、海棲哺乳類がついに地球の表舞台から消え去り、哺乳類と鳥類への世界へと移った新生代。下巻では、主に新第三紀と第四紀にスポットライトを当てます。現在につながる最後の時代を懸命に生きた生物たちの足跡にぜひご注目あれ。
目次
第2部 新第三紀(“ほぼ完成”した大陸配置;哺乳類!!哺乳類!!哺乳類!!!;孤高の大陸の哺乳類)
第3部 第四紀(そして「氷の時代」へ;“タール”に封じられた動物たち;最後の巨獣たち;続・孤高の大陸の哺乳類)
著者等紹介
土屋健[ツチヤケン]
オフィスジオパレオント代表。サイエンスライター。埼玉県生まれ。金沢大学大学院自然科学研究科で修号士を取得(専門は地質学、古生物学)。その後、科学雑誌『Newton』の記者編集者、サブデスク(部長代理)を経て2012年に独立し、現職。フリーランスとして、日本地質学会の一般向け広報誌『ジオルジュ』のデスク兼ライターを務めるほか、雑誌などの寄稿も多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
35
2016年刊。化石写真とイラストが美しいシリーズの最終巻。哺乳類が恐竜に代わって多様化。偶蹄類ではカリコテリウム類が面白い。顔と首は馬だけど、鋭いかぎ爪を持ちチンパンジーみたいにナックルウォークした。南米にはサーベルタイガーそっくりの有袋類やカピバラの巨大版(全長3m、体重1トン)。オーストラリアでは有袋類の捕食者が進化し、猫型・犬型のほか肉食カンガルーもいた。巨大なマンモスやナウマンゾウの化石も多数掲載されている。アシカやアザラシの祖先はカワウソそっくり。海の覇権は鯨に奪われたがペンギンと共に生き残った2025/12/17
ヨクト
23
シリーズ最終章。時代はマンモスやメガテリウム、メガロドンが跋扈する時代へ。人間の歴史の短さ、生物の歴史の途方もない長さに気づかされた。メガロドンの全身化石の発見を切に願う。そして、人類がいつまで繁栄するのか、そのあと台頭する生物とは。そんなことを考えちゃうね。2016/09/10
たまきら
21
読みおえたくなくてちびちび読み進めていたこの本。ああ…終わってしまいました。この時代の面白さは、日本の登場率が増えるところでしょうか。昔多摩川でナウマンゾウの化石が見つかった記事を読んで感激したけれど、「漁の網に結構よくかかる」とかもうびっくりです。あと、毛皮が残ってたりする「死体」が発見されるというのも興味深い。ラブレア博物館は本当に素晴らしかったなあ。敷地内にじめじめしたピットが結構あるんですけど、鑑賞後は子供たちが慎重にピットを迂回していておかしかった。ああ、オマケってなんなんだろう?2017/07/02
白義
15
十巻にも渡って古生物学の世界を案内してきたこのシリーズもここで一旦完結。マンモス、六メートルにも達するナマケモノのメガテリウム、三メートルにまでなるアルマジロのグリプトドンともはや滅びた巨大哺乳類たちが、本当に生命の歴史ではつい最近の、人類誕生前夜を盛り上げる。そんな彼らが滅んだ理由もまた人類という説とともに、地球規模の気候大変動もまた有力視されている。今の地球もいつ大変化を起こすか、生命のドラマは今も続いているのである。メガロドンと言えば超巨大サメが有名だが、二枚貝のメガロドンもいるというのは紛らわしい2017/03/20
更紗蝦
14
気候の変化と、それに伴う地形の変化が、生物の進化や絶滅にいかに影響を与えてきたかが、改めてよく分かる巻でした。このシリーズは、図版の多さもさることながら、個々の生物の栄枯盛衰を「地球の変化の歴史」とセットで重層的にイメージできるように工夫されているところが素晴らしかったです。2017/02/09