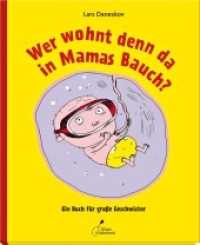目次
1 デボン紀の窓「フンスリュック」
2 陸の“最初の窓”が開く
3 大魚類時代の確立
4 大魚類時代の舞台
5 デボン紀後期の大量絶滅
6 脊椎動物の上陸作戦
著者等紹介
土屋健[ツチヤケン]
オフィスジオパレオント代表。サイエンスライター。埼玉県生まれ。金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。その後、科学雑誌『Newton』の記者編集者、サブデスクを担当。在社時代に執筆・編集した記事は、地球科学系を中心に宇宙から睡眠、ロボット、高校部活動紹介まで多数多彩。2012年に独立して現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
39
2014年刊。化石写真とイラストの充実したシリーズ。デボン紀は大魚類時代。前半は顎無し、後半は顎有りの魚が繁栄。表紙のダンクレオステウスは顎有りの板皮類。体長8〜10mで噛む力はホホジロザメ以上。シーラカンス類や肺魚類も栄えた。そして遂に陸上四足動物が現れる(この辺り特に面白い)。以下自分用メモ。⚫︎陸上では急速に緑化が進み、既に昆虫が成功している⚫︎アンモナイトは繁栄前夜。殻は真っ直ぐから巻きの強い方へ進化した⚫︎三葉虫は奇妙な形が花盛り⚫︎デボン紀後半の大量絶滅で三葉虫や腕足動物は大打撃を受ける。2025/08/02
Koning
34
時代の窓として化石の産地とそこで発掘された化石を紹介していくパターンはシリーズとして定着してる3冊目。冒頭でまさかのアノマロカリスさまの末裔がデヴォン紀に生きてたのか!ってのがあって、ビビる。なんか、こういうのを見るともしかすると深海には彼らの末裔がちっさくなって生存してる可能性もあるんじゃないか?なんて思いたくなったりするから素敵です(笑)。そして、いよいよ陸上へ進出する生物が出てきてみたり、魚類がわーっと出てきて海の中もにぎやかになってきたんだなーというのが判って楽しい。2014/10/03
更紗蝦
26
アンモナイトといえば、きっちりと殻が丸まった種類しか知らなかったので、丸まった形への進化の過渡期にあたる種類(殻の巻き方がゆるい)の存在は初めて知りました。アンモナイト類の殻の形も不思議ですが、「ファコプス類」と呼ばれる三葉虫の多様性も不思議です。トゲトゲのバリエーションが凄い!2016/11/01
ヨクト
24
本シリーズ第三弾。時代はついにデボン紀に。植物が地上へ進出し、魚類が海を支配する。シーラカンスが登場したのもこの時代。まさに生きた化石ですね。豊かなカラー写真や生物のイメージ画。頭の中にデボン紀の世界が広がる。末期の大量絶滅と脊椎動物の地上進出。次巻も楽しみ。2014/08/02
たまきら
21
3巻になると、現世生物の写真が大量に掲載されるようになり、時間というものの不思議さをより強く感じさせてくれる。また、発掘される場所があることの重要性も感じられる。その場所にその地層がなければ、私たちは全く彼らの存在を知らないのだ。今回も三葉虫の化石クリーニングの芸術度の高さに感激。ついに両生類が登場!足跡の痕跡化石は我が家のイモリを思わせます。植物についてもっと知りたい!2016/10/29