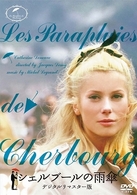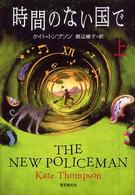内容説明
テレビでも話題の“はんだ付け職人”がそのノウハウを伝授!
目次
巻頭特集 これがはんだ付けの職人技だ!(最新電子技術を支えるはんだ付け;誰にでもできてしまうからこそ見過ごされてしまう「失敗」;はんだ付けの善し悪しは道具だてでほぼ決まる! ほか)
1 はんだ付け超入門(はんだ付けは、接着剤や溶接と何が違う?;なぜアルミやステンレスははんだ付けできないの?;はんだ付けの立役者「はんだ」の正体 ほか)
2 職人直伝!はんだ付けの基本技(電子回路とプリント配線;プリント基板の基礎知識;プリント基板への部品取付の鉄則 ほか)
著者等紹介
野瀬昌治[ノセマサハル]
1967年、滋賀県生まれ。1991年、島根大学理学部物理学科固体物理学科卒業。同年、関西NEC(株)入社。2004年(株)ノセ精機代表取締役社長。電子機器組立技能士。ホームページ『はんだ付けに光を』を通してはんだ付けのノウハウを公開。Dr.はんだ付け職人として、一般の方からのはんだ付け作業も請負中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tomoko 英会話講師&翻訳者
2
カラー写真入りではんだ付けの技術がよくわかる。はんだ付けの基礎知識からプリント基板のことまで。フラックスって何?という疑問を一発で解決してくれました。2014/06/29
Koki Miyachi
1
以前から少々苦手だったはんだ付けの指南書。何事にもコツがある。とても勉強になった。次回はんだ付けをやるのが楽しみだ。2016/03/30
仮定体
1
趣味の人が自己流でやっているはんだ付けの問題点を指摘する内容。まずは道具。ケーブル、コネクタの実例が多かった。 プロ向けには物足りない内容。(私は"プロ"ではないですが)2014/01/07
R
0
1年前に作ったものが壊れてしまう、自分のはんだ付けした基板をあとから見ると納得いかないなどがあり、はんだ付けのセットを買って練習し直した。道具やコテ先を変えるだけで、母材の温めやすさなどがぜんぜん違う。高い道具を売りつけるための文句だと思っていたが、これから先はハンダごてはちゃんとしたものを買うようにしようと思った。2021/02/05
-

- 電子書籍
- 神にホムラを ―最終定理の証明方法―(…
-
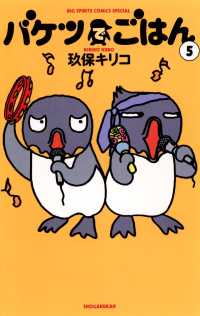
- 電子書籍
- バケツでごはん(5) ビッグコミックス