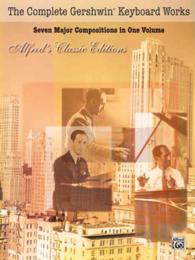- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
内容説明
1940~50年代に書き綴られながら、作家の出身国=スペインではフランコの死から3年後、1978年にようやく出版されたアヤラの短編集。「人びとの心の中の内戦」として展開した悲劇的なスペイン市民戦争の実相を市井の庶民の内省と諦観と後悔の裡に描く。
著者等紹介
アヤラ,フランシスコ[アヤラ,フランシスコ][Ayala,Francisco]
1906~2009。スペインの作家、社会学者。グラナダ生まれ。高校卒業後マドリードに引っ越し、前衛主義文学を推し進めた「27世代」の若手作家の一人として活動を始める。1923年マドリード大学法学部に入学、1925年初めての小説『魂なき男の悲喜劇』を発表。1931年法学博士を取得後、大学で教職に就く。1957年に渡米後はスペイン文学の教員として米国の名門大学のプリンストン大学、ニューヨーク市立大学、シカゴ大学などで教壇に立つ
松本健二[マツモトケンジ]
大阪大学世界言語研究センター准教授。ラテンアメリカ現代文学
丸田千花子[マルタチカコ]
東京生まれ。米国コロンビア大学大学院博士課程修了(Ph.D.スペイン文学)。専門はスペイン現代文学。慶應義塾大学経済学部専任講師、放送大学客員准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
52
ガルシアマルケスで衝撃が強すぎたスペインもの・・軽い作品はいくつか読んできたが、スペイン内戦の精神世界をえぐった最高傑作と称される当作を読むのが宿題になっていた。ロシアの牙の進撃を見続け、一層に。初のアヤラ。103歳で逝去とはさすがの大樹。この作品、内戦直後に執筆されたにもかかわらず、国民戦線の指揮を執ったフランコが倒れるまで36年間 封印の浮き身。40代入り口に立つアヤラが精力を傾けて取ったペンのパッションが際立つ・・かと言って決して荒ぶる文で無い。スペイン各地の日常風景、肩書のない人々が登場。だが2022/04/02
空崎紅茶美術館
12
スペイン内戦(1936~1939)を経験した人々の「心の中の内戦」に焦点を当てて書かれた五つの短編。ただタイトル買いしただけなのですが、作者本人による解説を含む「序」と訳注、訳者あとがきを読めば、おおまかに理解できます。内戦や戦争といったものは、それが起きている時よりも、終わってしまった後の方が苦しいと思う。生死に関わる状態であるならば、ただ生き残ることを考えればいい。でも、自由を得た後、それからも続く人生において、自己の体験をどのように消化するか。それは、難しい。2011/09/21
茎わかめろん
5
スペイン内戦を内側からえがいた短編集。戦いそのものではなく、前と後。スペイン内戦についても内戦についてもよく分からないまま読み終えてしまって、ちょっと対岸の火事のようにも感じるけど、殊更言いあげなくても人々の心に遺したものを読みながら思わずにはいられない。自分の心にも澱のようにたまっていくような。2012/07/22
メルセ・ひすい
3
15 “人々の心の中の内戦”として展開した、悲劇的なスペイン市民戦争の実相を、市井の庶民の内省と諦観と後悔の裡に描く。スペインではフランコの死から3年後、1978年にようやく出版されたアヤラの短編集。2011/06/02
サラ.K
2
オススメというほどでもないが、まずまずの作。ヨーロッパ映画のように始まりも終わりもない感じが漂う。内戦時のスペインを描いているが、筆は抑え目であり淡々としている。話の組み立て方はさすが。2011/12/08