内容説明
「帝国」の「戦争機械」が猛威を揮う時代に、未開社会における暴力=戦争の意義を考察する。人間の声に、人間的な言葉に耳を傾けるために。『千のプラトー』において、ドゥルーズ=ガタリが思い出を捧げたピエール・クラストルによる、未開社会の暴力をめぐる哲学的挑戦。
目次
暴力の考古学―未開社会における戦争(ピエール・クラストル)
クラストルの戦争論の理解をめざして 戦士に抗する社会―服従を拒否する社会における死と威光の交換(毬藻充)
著者等紹介
クラストル,ピエール[クラストル,ピエール][Clastres,Pierre]
1934‐1977。パリに生まれ、ソルボンヌ大学で哲学を学ぶ。人類学者で、南アメリカ先住民の神話を研究するアルフレッド・メトローのもとで、南アメリカ民族学をフィールドに選び、政治人類学者としての道を歩み始める。哲学者クロード・ルフォールらとともに雑誌『リーブル』の創刊に参加し、政治権力をめぐる問題を軸に論文を発表し始める。すべての文化は自民族中心的であることを免れ得ないとしても、「異民族文化抹殺的であるのはヨーロッパ文化だけである」と断言し、それは「多なるものを解消して一にしようとする同一化の原理」がはたらいているからだと喝破するなど、南アメリカ先住民社会を深く研究しつつ、それに基づいてヨーロッパ文明に対する徹底的な批判を展開した。不幸、自動車事故で夭折したが、形成途上にあったその理論は、フェリックス・ガタリの「戦争機械」概念をはじめ、急進的な現代フランス政治・哲学思想に影響を与え続けている
毬藻充[マリモミツル]
1950年生まれ。現在、同志社大学で哲学、京都精華大学ほかでフランス思想・比較思想史・現代ヨーロッパ論系の講義を担当
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sayan
roughfractus02
Mealla0v0
★★★★★
Kan T.
-

- 電子書籍
- 地獄祭【フルカラー】【タテヨミ】(36…
-
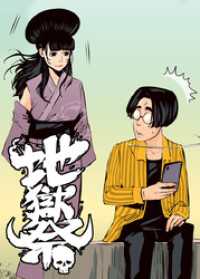
- 電子書籍
- 地獄祭【フルカラー】【タテヨミ】(38…







