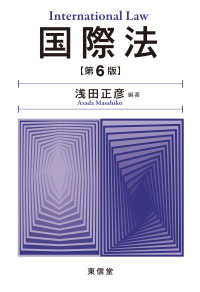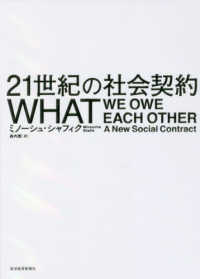内容説明
もっとたくさんの奴隷が解放できるはずだ。著者は本書で行動の指針を具体的に提案する。個人ができること。共同体の一員としてできること。政府や、市民としての私たちにできること。国連・世銀・世界貿易機関ができること。消費者、企業、政府ができること。開発組織、慈善団体と手を携えて私たちができること。
目次
五〇〇〇年の歴史
挑戦―新しい奴隷制の世界を理解するために
計画を立てる
現代奴隷の救出
自分の国で自由を育てよう
政府の役割―最強の圧力団体
地球規模の問題と射程
サプライチェーンを根元で断つ
貧困をなくして奴隷制に終止符を打つために、奴隷制をなくして貧困を撲滅する
奴隷制度の終わりの始まり
奴隷制度を撲滅するためにみなさんは何ができるか
著者等紹介
ベイルズ,ケビン[ベイルズ,ケビン][Bales,Kevin]
1947年生まれ。英国サリー・ローハンプトン大学社会学教授
大和田英子[オオワダエイコ]
1961年生まれ。アメリカ文学専攻。ニューヨーク州立大学Ph.D.。早稲田大学国際教養学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーなん
3
奴隷は過去の話ではない。現代のインド、アメリカそして日本にも存在する。衝撃的な写真や思わず現地の搾取現場の描写から、具体的な政策提言に至るまで包括的にこの問題を捉えることができる。奴隷コミュニティ全体による開放運動や彼らの社会復帰支援、企業・国家や世界レベルでの法整備・汚職排斥が筆者の主な解決策。ただ本文のレトリックが非常に多い。もう少し簡潔にまとめられるはず。概要をサッとつかみたい人はTEDで筆者の講演「現代の奴隷制度といかに戦うか」を聴くだけでも十分。こちらは非常によくできている。2014/01/06
あきら
0
最初の一頁目からかなりショックな写真が飛び込んできた。目の大きな男の子。肩から背中にかけてギザギザの傷痕。皮膚には穴があさいている。鞭で虐待を受けた痕だ。奴隷制なんて日本は関係ないじゃない?と思っている人が大多数だと思う。でもこの本では私たちの生活のなかにある奴隷によって作られた品々をあげている。そして世界でも有数の加害大国日本の問題が、書かれている。目を背けるわけにはいかない。少しでいい。自分にできることをしようと書いてある。希望はある。奴隷という非人間的な存在から逃げ出せた人達が希望として出てくるのだ2013/05/17
竹薮みさえ
0
もうね。ほんとに大変。人間てどれだけバカなんだろう。いったいなんで人をモノのように扱うんだろう。まったくわけがわからない。2012/12/07