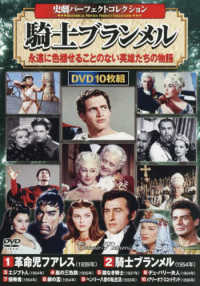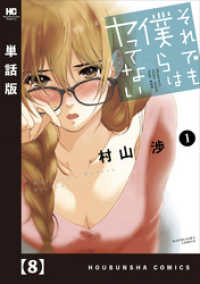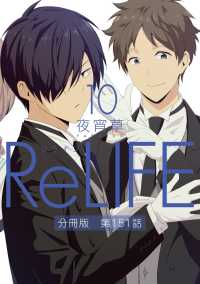出版社内容情報
光を分解すると虹のように色分かれします。虹のように分けられたその光の帯のことを〈光のスペクトル〉といいます。だから,虹は「天然の光のスペクトル」ということができます。〈分光器〉というものを使うと,いつでもどこでも簡単に光を虹の色に分けることができます。
第1幕
目次
第1幕 色とスペクトル(プリズムとホログラムシート;“回折格子板”を作る;簡易分光器 ほか)
第2幕 原子とスペクトル(蛍光灯のスペクトル;新しいタイプの蛍光灯のスペクトルは?;ろうそくの光を分光器で見たら ほか)
第3幕 太陽と星のスペクトル(フラウンホーファーが発見した“太陽スペクトルのなぞ”;太陽光線と白熱電球では、その連続スペクトルに違いはないか;太陽黒線のなぞにいどむ科学者の登場 ほか)
電磁波(=光と電波)、通信に関する発明発見の年表
著者等紹介
板倉聖宣[イタクラキヨノブ]
1930年、東京に生まれる。1953年、東京大学教養学部教養学科・科学史科学哲学分科を卒業。1958年、東京大学大学院数物系研究科を修了。物理学の歴史の研究によって理学博士となる。1959年、国立教育研究所に勤務(~95年)。1963年、科学教育の内容と方法を革新する「仮説実験授業」を提唱。1983年、編集代表として月刊誌『たのしい授業』(仮説社)を創刊。1995年、国立教育研究所を定年退職し、「私立板倉研究室」を設立。「サイエンスシアター運動」を提唱・実施し、その後さらに研究領域を広げて活躍中。仮説実験授業研究会代表、国立教育政策研究所名誉所員
湯沢光男[ユザワミツオ]
1956年、栃木県宇都宮市に生まれる。1978年、宇都宮大学教育学部(理科)を卒業。小学校教諭となる。1982年、仮説実験授業と巡り合い、一気にのめり込む。1988年、自ら希望して中学校に転勤。2007年、「東レ理科教育賞」を受賞。現在、宇都宮市雀宮中学校教頭、仮説実験授業研究会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
IGBB