- ホーム
- > 和書
- > エンターテイメント
- > TV映画タレント・ミュージシャン
- > ミュージシャンの本
内容説明
音楽評論家・市川哲史による渾身のV系総論!
目次
第1章 私が“V系”だった頃(21世紀version)(XとLUNA SEAの“再結成”で考えた、いろんなこと;生き残った者たちの、それぞれの“正義” ほか)
第2章 “V系”がヤンキー文化だった頃(ハレだ祭りだヤンキーだ“V系オールドスクール”再考;YOSHIKI伝説フォーエバー)
第3章 “V系”がオタク文化になった頃(ゴールデンボンバー売れっ子大作戦;鬼龍院翔も“V系カリスマ”である、たぶん ほか)
第4章 私が“hide”と呑み倒してた日々(hideと私と愉快な“元・ロック少年”たち;すべての後輩たちの“hide兄ぃ(J談)” ほか)
著者等紹介
市川哲史[イチカワテツシ]
1961年岡山県生。音楽評論家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なる
29
ヴィジュアル系を少しでも齧っていれば知らない人はいない市川哲史による聖典のような分厚さの本。XやLUNA SEAに代表され世界へ拡散した一大ムーブメントであるヴィジュアル系を、最も近い場所で見ていた外部の人間として冷静かつ愛に溢れた目線でのツッコミと分析が語られていて読み応え充分。ヴィジュアル系がいかに形作られたか文化人類学的に解説していたり(いちいち頷いてしまう内容)、黎明期の関係者(バンドマンを含め多数)との対談もたっぷり。わざわざ字を小さくしているのに脚注だけで28ページ(1項目3ページあるのも)。2021/09/07
ひろ
16
ヴィジュアル系の中でも、いわゆるネオヴィジュアル系が好き。今の土壌が生まれた歴史を知りたくて手を取った。レジェンドであるX JAPAN、BUCK-TICK、LUNA SEAなどの時代から続くシーンの変遷が、インタビューを通じて語られる。最近の情勢に関しては情報少なめ。ルナフェスで初めて知った過去の諸先輩バンドと、現在のヴィジュアル系に明らかな色の違いがある理由も納得。ただ、ある程度の知識がないと読み進めるのはきつそう。結論、なんでもありの表現の場となった、現代のヴィジュアル系はやっぱり面白い。2020/11/29
さんつきくん
8
2000年代に入って、XやLUNA SEAが再結成された。ゴールデンボンバーはどでかい一発を放った。Xはヤンキーみたいな暴力的な音楽だった。見た目も世間に対して反抗的だった。90年代後半にV系がブームに。悪の雰囲気もありつつ、それでいてカッコいいお兄さんがV系のロックをやってたイメージ。00年代はホストに近くなり、その後はオタクがロックをやっている。読んでいるとそんなイメージが確立する。バンギャさんへのインタビュー記事も興味深い。地方出身者が多いのが特徴らしい。2023/08/01
kthk arm
4
2022年90冊目。Xの命がけのレコーディングやら、YOSHIKIの人となり、hideとの回想と完全に中の人視点での、裏側を見せていただき、もう、サイコーでした。もちろん、LUNA SEAからPIERROTまで、界隈の話盛りだくさん。 読んでて、改めて、BUCK-TICKが別次元でスゴいのか再確認。 ただ、中盤の00年代以降のバンギャ文化はいまひとつ共感できなかった。 2022/08/31
AiN
4
内容紹介 ゴールデンボンバーは〈V系〉の最終進化系だったーー? 80年代半ばの黎明期から約30年、日本特有の音楽カルチャー〈V系〉とともに歩んできた音楽評論家・市川哲史の集大成がここに完成。X JAPAN、LUNA SEA、ラルクアンシエル、GLAY、PIERROT、Acid Black Cherry……世界に誇る一大文化を築いてきた彼らの肉声を振り返りながら、ヤンキーからオタクへと受け継がれた“過剰なる美意識"の正体に迫る。 ゴー ルデンボンバー・鬼龍院翔の録り下ろしロング・インタビューほか、狂乱のル2017/03/28
-
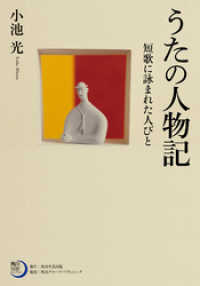
- 電子書籍
- うたの人物記 短歌に詠まれた人びと 角…
-
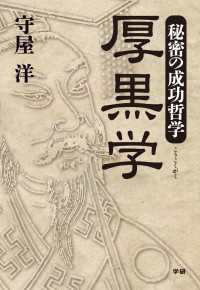
- 電子書籍
- 秘密の成功哲学 厚黒学 - リーダーと…




