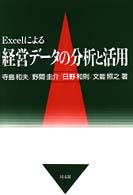内容説明
文学者小泉八雲の日本語の謎に迫る。日本にも存在した居留地のピジン日本語とは?明治期の言語教育者、法律家、外交官、間諜たちの日本語教育の魅力を探る。
目次
第1部 小泉八雲と日本語(「ヘルンさん言葉」考察―言語教育ならびに社会言語学的視座から;「ヘルンさん言葉」における小泉セツの調整日本語;「ヘルンさん言葉」とクレオール語;「ヘルンさん言葉」と「簡約日本語」;ハーンの訳読教授法と幕末明治期の文法訳読教授法の比較考察)
第2部 明治期の日本語研究・日本語教授法をめぐって(幕末明治期の居留地における日本語についての考察―YOKOHAMA DIALECTを中心に;オレンドルフ教授法の受容の考察―井上勤の受容から岡倉由三郎の外国語教授論まで;馬場辰猪『日本文典初歩』の考察―動詞分類の特徴ならびに出現背景を中心に;馬場辰猪『日本文典初歩』における練習問題の考察;馬場辰猪『日記』から見た『日本文典初歩』第2版の考察―成立および特色を中心に ほか)
著者等紹介
金沢朱美[カナザワアケミ]
大阪生まれ。大阪外国語大学卒業。大阪府立女子大学を経て筑波大学大学院教育研究科修了。現在目白大学外国語学部、同言語文化研究科日本語・日本語教育専攻教授。日本語教育史、社会言語学を専門分野として研究を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。