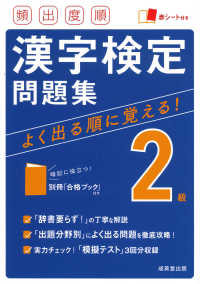内容説明
親子の関係は一方通行ではなく相互に影響し合うものです。子どもにネガティブに接すれば反抗が返ってきますし、子どもの反応によって親は子どもをほめたり叱ったりします。ペアレントトレーニング(ペアトレ)では、子どもからよい反応を得たいと思ったら、親が先に肯定的な注目を与えることが重要だと考えます。
目次
子どもの行動を3種類に分けてみよう!
好ましい行動を増やそう!
好ましくない行動を減らそう!
子どもの協力を増やそう!
行動チャートを作ろう!
制限を設けよう
園・学校と連携しよう
まとめ
著者等紹介
らせんゆむ[ラセンユム]
イラストレーター、マンガ家、二児の母。二人の息子を育てるうちに特性が気になり始め、自治体のペアレントトレーニングに通いながら育て方を学ぶ
庄司敦子[ショウジアツコ]
まめの木クリニック心理士(臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士)。1993年、東北福祉大学社会福祉学部福祉心理学科卒業。国立精神・神経センター精神保健研究所児童・思春期精神保健部研究生、流動研究員を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう
4
ペアレントトレーニング(PT)を実施する専門家に向けて書かれたのではなく、PTを受ける保護者に向けて書かれた書籍。PTを実施する際に、資料を準備する必要があるが、本書籍を活用するとよいだろう。それくらいわかりやすくまとまっている。 実際の参加では伺い知ることしかできない、他参加者の思いや困り感を漫画にしており、参加継続の動機付けに繋がるだろう。 進行側に必要な資料としては、同著者が所属するまめの木クリニックの皆さんが編集された「こうすればうまくいく発達障害のPT実践マニュアル」を活用したい。2023/07/11
yukari
2
ペアトレのやり方について書いてある。シンプルで分かりやすい。大事なのは子どもをほめる機会を増やすこと。まず子どもの行動を好ましい、好ましくない、許せない行動(人や自分に危害が及ぶなど)に分けて、1つ目はほめる、2つ目は無視する(注目しないがやめたらほめる)、3つ目は叱る、とする。子どもに指示するときはCCQ(Close,Calm,Quiet)で繰り返す、が参考になった。ついイラッとして語気が強くなってしまうことがあるのでCCQは心がけたい。2024/03/26
うっかり呑兵衛
1
公共図書館。「ペアレントトレーニング」の略、「育てにくい」特性のある子への親のアプローチが提示されている。まだ早いので必要そうならまた読みたい。一方で仕事でもこの「育てにくい」傾向のある子がいるが、こうした知見を活かした10代向けへのアプローチも勉強しないとなと改めて思った。2025/01/21
kanamiiiiin
1
子供の行動を変えるために、どう親が関わっていくか。マンガだから読みやすいし、状況のイメージがわきやすかった。しっかり読み込みたい。2024/10/04
-
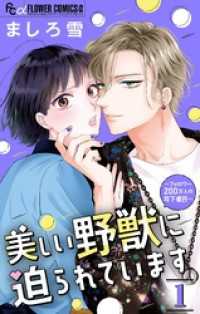
- 電子書籍
- 美しい野獣に迫られています~フォロワー…