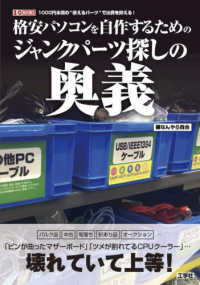出版社内容情報
子どもの傷つけられた体験を理解し、子どもを救うためにはどうサポートしていけばいいのかを考えます。
■杉本彩さん推薦! 悩みや苦痛を抱えたときに一人で抱え込み、誰にも助けを求めないこと。これこそが最大の自傷的な行動であり、同時に、子どもの将来における自殺リスクを高める根本的な要因なのです。
子どもの傷つけられた体験を理解し、子どもを救うためにはどうサポートしていけばいいのかを考えます。
■杉本彩さん推薦!
第1章 自傷とは何か
1 自傷の実態
2 自傷の手段・方法
3 なぜ自傷するのか
4 自傷と自殺の違い
5 自傷の定義
第2章 自傷のメカニズムに関する仮説
1 自傷の神経生物学的モデル
2 神経生物学的モデルの背景にある生育環境
3 自傷と解離の関係
4 暴力の観察学習
5 自傷の伝染性とメディアの影響
第3章 自傷というアディクションーー死への迂回路
1 アディクション~気分を変えるための行為
2 自傷はアディクションなのか
3 自傷のアディクション化プロセス
4 自傷から過量服薬へ
5 過量服薬をするリスクの高い若者の特徴
6 自傷から自殺へ
第4章 援助にあたっての心構え
1 援助者は「氷山の一角」しか知ることができない
2 傷のケアをしないことも自傷
3 援助希求能力の芽を摘まないこと
4 自傷に向き合う際の注意点
5 親に内緒にしてほしい!?
6 援助者の援助希求能力も大切である
第5章 対応の実際
1 自傷に関する情報を大ざっぱに収集する
2 精神科に紹介する際の判断基準
3 精神科に紹介したらそれで終わりではない
4 自傷に関する情報を詳しく収集する
5 置換スキルの習得
6 自傷する若者との面接の実際
7 自傷が止まった後で
8 「死にたい気持ち」に気づくこと
9 「死にたい」と考える人にかかわり、つなげること
第6章 家族と学校に伝えたいこと
1 家族への働きかけ
2 学校における自傷の伝染防止策
3 学校における自傷・自殺予防プログラムのあり方
松本 俊彦[マツモト トシヒコ]
著・文・その他
目次
第1章 自傷とは何か
第2章 自傷のメカニズムに関する仮説
第3章 自傷というアイディクション―死への迂回路
第4章 援助にあたっての心構え
第5章 対応の実際
第6章 家族と学校に伝えたいこと
著者等紹介
松本俊彦[マツモトトシヒコ]
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター副センター長/薬物依存研究部診断治療開発研究室長。平成5年佐賀医科大学医学部卒業後、横浜市立大学医学部附属病院にて臨床研修の後、国立横浜病院精神科、神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科、国立精神・神経センター精神保健研究所司法精神医学研究部などを経て、平成19年より同研究所自殺予防総合対策センター自殺実態分析室長、平成20年より薬物依存研究部室長を併任、平成22年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
ぼりちゃん
たかこ
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
くさてる