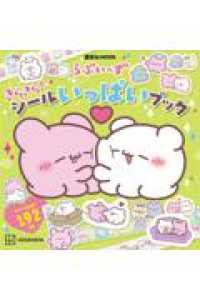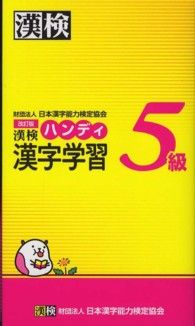内容説明
支援の現場で出合う暴力は、本質的には防止や制圧をするものではなく、クライエント自身が主体的選択として「手放す」ものである。しかし、クライエントは欲求や感情を言葉ではなく暴力という対処行動として表出し、そのことに苦しむ場合でも自ら援助を求めることはほとんどない。なぜなら、援助を求めるとは欲求や感情を言葉で表出することそのものだからである。その結果、暴力を振るうクライエントへの支援は困難を極めることになる。本書では、暴力の定義、起源、要因を解説し、医療・司法・福祉各領域におけるDVや児童虐待への支援実践を概観しながら、思春期以降の児童から成人までを対象とした暴力を手放すための四つのフェーズからなる支援モデルとセラピストの適切な「ありよう」を提示する。また、児童による性暴力と施設における暴力についての支援モデルを適用した二つの事例と、最終章で著者が提言する「情理の臨床」を通して、暴力を手放す臨床心理学的支援に迫る。
目次
第1章 手放す支援の難しさ
第2章 暴力の起源を辿る
第3章 暴力が生じる要因とその影響
第4章 各領域の支援を概観する―医療、司法、福祉を中心に
第5章 DVと児童虐待の支援を概観する
第6章 手放す支援のモデル
第7章 セラピストのありよう
第8章 事例を通じて理解を深める(1)―性暴力の事例
第9章 事例を通じて理解を深める(2)―施設における暴力
最終章 「情理の臨床」としての手放す支援
著者等紹介
佐々木大樹[ササキダイキ]
愛知県立時習館高等学校卒業後、大阪大学人間科学部、中京大学大学院心理学研究科を経て、京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。高校時代は生命科学の研究に関心を持つ。その後、人間科学(学士)・心理学(修士)・教育学(博士)と異なる学問領域で学位を修める。日本心理臨床学会学術誌編集委員(第7期)。神田橋條治医師に師事し、10年にわたり陪席。公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士スーパーバイザーの他、産業カウンセラーの資格を持ち、大手企莱でのキャリアカウンセリング経験もある。愛知県入庁後は、児童相談所で心理職を15年、福祉職を2年務め、専門職向け研修も多数担う。現在、東海学園大学心理学部准教授/愛知県海部児童・障害者相談センター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろか
saiikitogohu