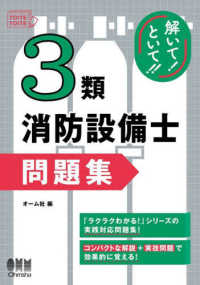出版社内容情報
パット・デニング[デニング・パット]
著・文・その他
ジーニー・リトル[リトル・ジーニー]
著・文・その他
松本 俊彦[マツモト トシヒコ]
監修
高野 歩[タカノ アユミ]
監修
古藤 吾郎[フルフジ ゴロウ]
監修
新田 慎一郎[シンデン シンイチロウ]
監修
内容説明
薬物・アルコールの使用や誤用による「ハーム(害)」を「リダクション(低減)」するための具体的なメソッドが解説された日本で最初の実践書。「ダメ。ゼッタイ。」や「断酒・断薬」などの「やめるか/やめないか」だけにとらわれず、自分に合ったより安全でより健康的な使用方法や減薬・減酒/断薬・断酒へのステップを一歩ずつ進め、今より少しでも暮らしやすく・生きやすくしていくためのプロセスが学べる一冊。
目次
なぜハームリダクションなのか?
ハームリダクションへようこそ
なぜ薬物を使うのだろう…?
薬物使用はどこからハームになるの?
なぜ問題になる人とならない人がいるの?
困りごとに気づくためには
どう変わっていくの?
変わることをあきらめる必要はない
物質使用マネジメント
使っているときのセルフケア〔ほか〕
著者等紹介
デニング,パット[デニング,パット] [Denning,Patt]
Ph.D.。2000年にJeannie LittleとサンフランシスコにHarm Reduction Therapy Center(HRTC)を設立し、カウンセリング・サービスとトレーニングのディレクターに就任。薬物使用のセラピーに加え、他のメンタルヘルス・心理分野の臨床家であり、ハームリダクションの心理療法を開発し発展させてきた専門家の一人である
リトル,ジーニー[リトル,ジーニー] [Little,Jeannie]
LCSW(licensed clinical social worker)。HRTCの事務局長。認定グループ心理療法士。グループワークにハームリダクションセラピーを初めて導入し、以降は多様なコミュニティに幅広くハームリダクションセラピーを応用している
松本俊彦[マツモトトシヒコ]
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長。1993年佐賀医科大学卒業。横浜市立大学医学部附属病院にて臨床研修修了後、国立横浜病院精神科、神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科を経て、2004年に国立精神・神経センター(現、国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所司法精神医学研究部室長に就任。以後、同研究所自殺予防総合対策センター副センター長などを歴任し、2015年より現職。2017年同センター病院薬物依存症センターセンター長併任
高野歩[タカノアユミ]
東京医科歯科大学精神保健看護学分野。千葉大学看護学部看護学科卒業後、看護師として精神科・内科で勤務。久里浜医療センター勤務時代にアルコール依存症の治療に携わる。その後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻に入学し、博士(保健学)を取得。大学院生の頃から、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部にて薬物依存症に関する研究に従事。物質依存や行動嗜癖の研究を行う中でハームリダクションに関心を持ち、海外のハームリダクション活動の視察や論文執筆等を行っている
古藤吾郎[コトウゴロウ]
ハームリダクション東京/日本薬物政策アドボカシーネットワーク(NYAN)/NPO法人アジア太平洋地域アディクション研究所(アパリ)。2005年、米国コロンビア大学大学院ソーシャルワーク修士課程修了。ハームリダクション(HR)を実践する2つのNGOで実習。帰国後、NPO法人アパリにてHRに基づく活動を開始。これまでに世界15カ国以上の都市で開催されたHR分野の会議や研修に参加、イベントや学会等に登壇。日本で暮らす難民たちの生活支援や、DV加害者男性の教育プログラムにも従事。東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野協力研究員。2015年にNYAN|日本薬物政策アドボカシーネットワークを立ち上げ、2021年に上岡陽江とともにハームリダクション東京を設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
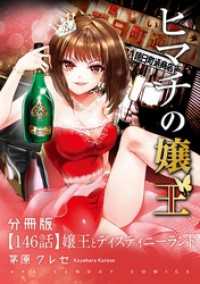
- 電子書籍
- ヒマチの嬢王【単話】(146) マンガ…
-
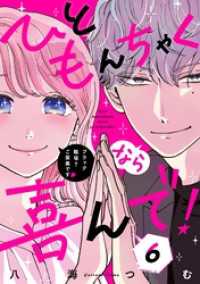
- 電子書籍
- ひともんちゃくなら喜んで!【単話】(6…
-
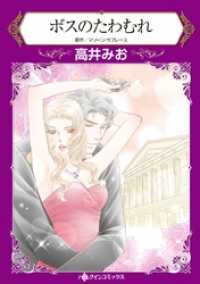
- 電子書籍
- ボスのたわむれ【分冊】 7巻 ハーレク…
-
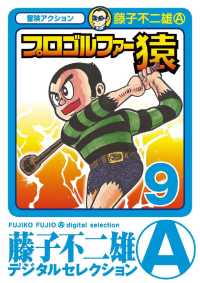
- 電子書籍
- プロゴルファー猿(9) 藤子不二雄(A…