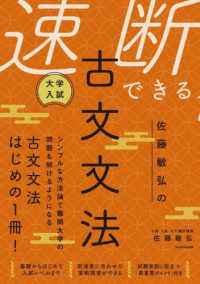出版社内容情報
友だちはほしいけれど不安やこだわりで前に進めなくなってしまう、思春期の複雑な対人関係を前に立ちすくんでしまう……発達障害の特性のなかでも人との関係に課題を抱えている子どもたちに、友だち作りのソーシャルスキルを提供する「PEERS(Program for the Education and Enrichment of Relational Skills)」。「PEERS」には他のプログラムにはない4つの特徴がある――?自閉スペクトラム症をはじめとする社会性に課題のある子どもたちが苦手とするスキルにフォーカスしていること、?思春期の子どもを対象にしていること、?子どもと保護者の同時参加によってスキルの般化を目指すこと、?プログラムの効果が科学的に証明されていること。さらに「PEERS」では2つの場面で体験しながら友だち作りのスキルを学ぶ――?家庭では親子でいっしょにホームワークに取り組む、?グループセッションでは仲間たちのロールプレイや行動リハーサルを通して自分を振り返るフィードバックを受ける。
ひとつひとつ課題をクリアできるように設計された全14セッションをトレーナーといっしょにこなしていけば、学んだことを学校でもすぐに応用できるなど、親子で効果を実感できる工夫があちこちに盛り込まれ、保護者と思春期・青年期の子どもたちに向けて「PEERS」の内容をまとめた『友だち作りの科学』(2017)と併用すれば、もっと上手にもっと効果的に「PEERS」を使いこなせるようになる。友だちを見つけて楽しく明るく日々を送るための、友だち作りがみるみる身につく「PEERS」トレーナーマニュアル!
エリザベス・A・ローガソン[エリザベスエーローガソン]
著・文・その他
フレッド・フランケル[フラッドフランケル]
著・文・その他
山田 智子[ヤマダ トモコ]
監修/翻訳
大井 学[オオイ マナブ]
監修/翻訳
三浦 優生[ミウラ ユウセイ]
監修/翻訳
内容説明
友だちはほしいけど不安とこだわりで前に進めない、複雑な思春期の人間関係に立ちすくんでしまう…自閉スペクトラム特性のなかでも人との関係に課題を抱える子どもたちに友だち作りのスキルを提供する、UCLAで開発された「PEERS(Program for the Education and Enrichment of Relational Skills)」。ひとつひとつ課題をクリアできて効果を実感できるように設計された14セッションをこなしていく、トレーナーのためのとっておきのヒントを紹介。思春期の子どもと保護者が取り組めるセルフヘルプガイド『友だち作りの科学』(金剛出版(2017))と併用すれば、もっと上手にもっと効果的に「PEERS」を使いこなせるようになる。友だちといっしょに楽しい毎日を送るための、友だち作りがみるみる身につく「PEERS」トレーナーマニュアル!
目次
1 はじめに(このマニュアルの使い方;必要とされるスタッフ ほか)
2 プログラムを始める準備(スクリーニング(参加者を選ぶ)
電話スクリーニングの流れ ほか)
3 セッション(セッション1:導入と会話のスキル1―情報公換;セッション2:会話のスキル2―双方向会話 ほか)
Appendices(評価尺度;セッション資料)
著者等紹介
ローガソン,エリザベス・A.[ローガソン,エリザベスA.] [Laugeson,Elizabeth A.]
Psy.D.自閉スペクトラム症や社会性に課題のある子どもや思春期の若者へのソーシャルスキルトレーニングを専門とする臨床心理学者。UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behaviorの精神医学・行動科学学部のAssistant Clinical Professorであり、The Help Group‐UCLA Autism Research Allianceのディレクターでもある。また、UCLA Children’s Friendship and Parenting ProgramのサブディレクターとUCLA Early Childhood Clubhouse Programのディレクターも務めている2004年にPepperdine Universityから博士号を授与された。そして2007年にはUCLAでポストドクターリサーチフェローシップNHIT32を受け、博士研究員として研究を修了している。自閉スペクトラム症、知的障害、胎児性アルコール症候群(FASD)、注意欠如多動症(ADHD)の子どもたちへのソーシャルスキルトレーニングに関する数多くの効果研究の主席研究員であり、それらの共同研究にも取り組んでいる
フランクル,フレッド[フランクル,フレッド] [Frankel,Fred]
PhD.UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behaviorの精神医学・行動科学学部の医療心理学専門の教授。UCLA Children’s Friendship and Parenting Programの創設者であり、ディレクター。ADHDと自閉スペクトラム症の子どもたちのためのソーシャルスキルトレーニングに関する、National Institute of Mental Health(NIMH)から助成を受けた2つの研究の首席研究者であり、Centers Disease Control and Prevention(CDC)―胎児性アルコール症候群の子どもたちのためのソーシャルスキルトレーニングの研究の共同主任研究者(PI(主席研究者):Mary O’Connor)。そして子どもの精神病に関する学際的な研究への助成金を受けている(PI:Peter Tanguay)。また、NIHの助成を受けたAutism Intervention Research Network Center(PI:Connie Kasari)とDrown Foundation-funded pediatric overweight prevention grant(PI:Wendy Slusser)の共同研究者でもある。これまでに自閉症、ADHD、発達障害、胎児性アルコール症候群、小児肥満についての46本以上のレビュー研究論文を発表してきた
山田智子[ヤマダトモコ]
UCLA PEERS Certified Provider(Adolescent & School Based & Young Adult Program)。臨床心理士、特別支援教育士。京都教育大学非常勤講師。大阪府公立学校チーフスクールカウンセラー。教育相談員。大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学:連合小児発達学研究科(博士後期課程)単位取得満期退学。サンタクララ大学大学院(米国カリフォルニア州)カウンセリング心理学修士
大井学[オオイマナブ]
京都大学大学院教育学研究科博士課程中退。教育学博士。愛媛大学助手/講師、金沢大学教育学部助教授/教授、九州大学大学院人間環境学府客員教授、大阪大学大学院連合小児発達学研究科教授
三浦優生[ミウラユイ]
国際基督教大学大学院教育学研究科修士課程修了、京都大学大学院理学研究科博士課程満期退学。教育学修士。金沢大学子どものこころの発達研究センター特任助教、大阪大学大学院連合小児発達学研究科助教、愛媛大学教育・学生支援機構英語教育センター講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
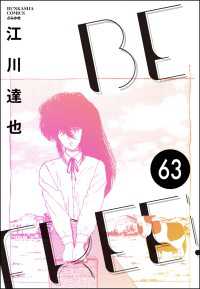
- 電子書籍
- BE FREE(分冊版) 【第63話】…
-

- 電子書籍
- ローズガーデンの贈り物【分冊】 11巻…