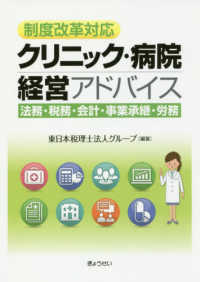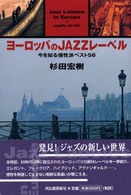出版社内容情報
入院から外来へ,不問から対話へと展開してきた森田療法。その理論的枠組みと具体的な介入法・技法をわかりやくす紹介する。
幅広い対象への適応を目指し,入院森田療法から外来森田療法へと主たる治療のシステムが変化していった森田療法。本書では,実際に外来患者を前にして,問題点をどのような枠組みで理解し,どのような介入を行い,それがどのような変化を引き起こすのかを紹介する。
第1章では森田療法の臨床の知の根っこに“自然”という理解が存在することを解説。第2章では森田自身の治療実践,赤面恐怖の介入法と治療経過をとおして,森田療法では症状そのものを直接扱わない(不問)という原則を確認し,第3章では,森田療法のメタサイコロジーというべき自然論について解説する。第4章では,森田療法の治療目標である「あるがまま」と,「とらわれ」という対極的なあり方を説明。第5章から第9章までは,治療の実践編として治療時期ごとの介入法とクライアントの変化,家族への介入法を紹介する。そして,森田療法の実践をさらに深く理解するために,第10章から第12章までは,異なった臨床フィールドを持つ森田療法家による事例を提示する。第13章では外来森田療法のガイドライン(日本森田療法学会)の解説と認知行動療法との比較をし,終章では,現代における森田療法の役割を考察する。
森田療法の最新技法を学べる一冊。
まえがき
第1章 臨床の知としての森田療法
第2章 森田の臨床実践
第3章 森田療法の基本的考え方─自然/反自然の枠組みから
第4章 「とらわれ」と「あるがまま」
第5章 治療の実践─―初回面接:問題の読み直しと治療導入
第6章 治療の実践─―治療前期:症状をめぐって
第7章 治療の実践─―治療中期:自己のあり方をめぐって
第8章 治療の実践─―治療の後期と終了:あるがままに生きる
第9章 治療の実践─―家族への介入
第10章 事例検討─―パニック障害
第11章 事例検討─―過適応主婦のうつ病
第12章 事例検討─―強迫性障害
第13章 外来森田療法のガイドライン
終章 森田療法と現代社会
文 献
索 引
【著者紹介】
●編者略歴:
1970年 東京慈恵会医科大学卒業
1979年東京慈恵会医科大学第三病院精神神経科科長(森田療法室に勤務,入院森田療法を主として行う),精神医学教室助教授,成増厚生病院に勤務後,1996年森田療法研究所・北西クリニック(自費診療の外来森田療法専門クリニック)を開設し,現在に至る。
2001年4月から2011年3月まで日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授。
慢性抑うつ,不安に悩む人たちに外来森田療法やそれに基づいた家族への介入,グループワークなどを行っている。
内容説明
幅広い対象への適応を目指し、入院森田療法から外来森田療法へと主たる治療のシステムが変化していった森田療法。本書では、実際に外来患者を前にして、問題点をどのような枠組みで理解し、どのような介入を行い、それがどのような変化を引き起こすのかを紹介する。森田療法の最新技法を学べる一冊。
目次
臨床の知としての森田療法
森田の臨床実践
森田療法の基本的考え方―自然/反自然の枠組みから
「とらわれ」と「あるがまま」
治療の実践―初回面接:問題の読み直しと治療導入
治療の実践―治療前期:症状をめぐって
治療の実践―治療中期:自己のあり方をめぐって
治療の実践―治療の後期と終了:あるがままに生きる
治療の実践―家族への介入
事例検討―パニック障害
事例検討―過適応主婦のうつ病
事例検討―強迫性障害
外来森田療法のガイドライン
森田療法と現代社会
著者等紹介
北西憲二[キタニシケンジ]
1970年東京慈恵会医科大学卒業。1979年東京慈恵会医科大学第三病院精神神経科科長(森田療法室に勤務、入院森田療法を主として行う)、精神医学教室助教授、成増厚生病院に勤務後、1996年森田療法研究所・北西クリニック(自費診療の外来森田療法専門クリニック)を開設し、現在に至る。2001年4月から2011年3月まで日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授。慢性抑うつ、不安に悩む人たちに外来森田療法やそれに基づいた家族への介入、グループワークなどを行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。