出版社内容情報
好評の前書を大幅に加筆・修正。解離性障害,自己破壊的行為,発達障害,薬物療法論を加えた,思春期精神科臨床の決定版である。
思春期臨床は,精神疾患の患者のみを扱うわけではない。家庭や学校における青年の呈する幅広い問題行動を対象とする。これらの青年の問題行動は,欧米の診断基準に拠れば,パーソナリティ障害,適応障害,発達障害等に診断されるが,著者はこれらをマニュアル的に診断するだけでなく,クライアント一人ひとりの個別性を尊重したアプローチを展開する。また,思春期臨床は,クライアントの現実の「人生の質・生活の質」を向上させるものでなければならない。青年と家族がどのような問題を抱え,何を求めているのか,そして,治療者が何を提供できるのか,何を提供するのが望ましいのか,著者は,思春期の心の臨床を実践する際の基本的視点と面接をすすめるにあたっての原則を平易な文章で述べる。
本書は,好評の前書にその後の臨床的蓄積から加筆・修正を行い,さらに解離性障害,自己破壊的行為,発達障害,薬物療法に関する論考を加えた増補決定版である。日常臨床からフィードバックした心理療法面接に関する臨床的知見の宝庫といえよう。
□第?T部 思春期臨床の基本的視点
思春期の治療を引き受ける時
児童青年期の臨床的発達論
青年の内的世界と現実―能動性と受動性―
思春期における薬と精神療法
思春期における支持的精神療法
集団体験について(その1)―ひきこもり青年とたまり場―
集団体験について(その2)―さまざまな「動き」を通して―
*エッセイ:精神医学における曖昧さと明確さ
□第?U部 思春期面接の現場から―治療と援助の実際―
思春期面接のすすめ方
青年期患者に対する森田療法的アプローチ―対人恐怖症の症例―
*エッセイ:家族の姿
不登校を考える
境界例
摂食障害
ヒステリー(1)―転換性障害―
ヒステリー(2)―解離性障害―
強迫性障害―主として不潔恐怖を中心として―
青年期の自己破壊を考える
青年と不安
広汎性発達障害に対する精神療法的アプローチ
私なりの精神療法,心理療法の学び方
*エッセイ:民芸と精神科治療
あとがきに代えて―癒しの鳥―
内容説明
本書は、好評の前書にその後の臨床的蓄積から加筆・修正を行い、さらに解離性障害、自己破壊的行為、発達障害、薬物療法に関する論考を加えた増補決定版である。日常臨床からフィードバックした心理療法面接に関する臨床的知見の宝庫といえよう。
目次
第1部 思春期臨床の基本的視点(思春期の治療を引き受ける時;児童青年期の臨床的発達論;青年の内的世界と現実―能動性と受動性;思春期における薬と精神療法;思春期における支持的精神療法;集団体験について その1―ひきこもり青年とたまり場;集団体験について その2―さまざまな「動き」を通して)
第2部 思春期面接の現場から―治療と援助の実際(思春期面接のすすめ方;青年期患者に対する森田療法的アプローチ―対人恐怖症の症例;不登校を考える;境界例;摂食障害;ヒステリー 1―転換性障害;ヒステリー 2―解離性障害;強迫性障害―主として不潔恐怖を中心として;青年期の自己破壊を考える;青年と不安;広汎性発達障害に対する精神療法的アプローチ;私なりの精神療法、心理療法の学び方;あとがきに代えて―癒しの鳥)
著者等紹介
青木省三[アオキショウゾウ]
1977年岡山大学医学部卒業、同大学医学部附属病院神経精神科研修医。1978年慈圭病院(岡山市)。1979‐1992年岡山大学医学部附属病院神経精神科医員、助手、講師。1993年岡山大学医学部神経精神医学教室助教授を経て1997年より川崎医科大学精神科学教室教授。その間、1988、1990‐1991年、英国ベスレム王立病院(青年期ユニット)、モーズレイ病院、ロンドン大学精神医学研究所に留学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
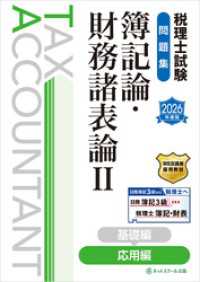
- 電子書籍
- 税理士試験問題集簿記論・財務諸表論Ⅱ応…
-
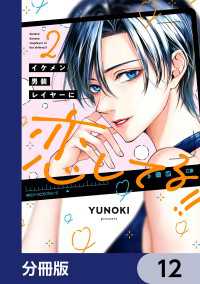
- 電子書籍
- イケメン男装レイヤーに恋してる!!【分…
-
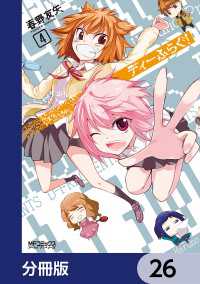
- 電子書籍
- ディーふらぐ!【分冊版】 26 MFコ…
-

- 電子書籍
- リベンジH 分冊版 9 アクションコ…
-
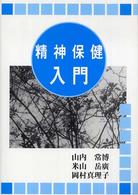
- 和書
- 精神保健入門



