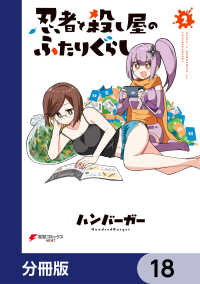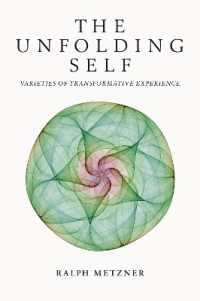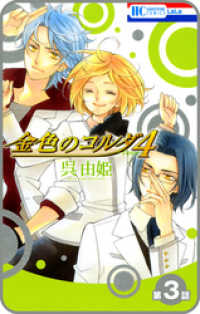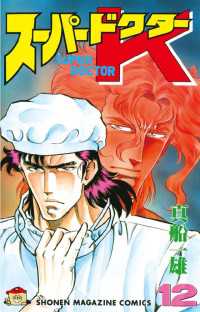- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学外科系
- > リハビリテーション医学
出版社内容情報
作業療法を,考え方や使い方に関する「知」,実践のコツにあたる「技」,センスを伝える「理」に分けてまとめた懇切な技法指導書。
作業療法は,治療・援助にあたる者と対象者との協同の営みであり,その過程は作業を介したコミュニケーションの成立プロセスといえる。言葉が機能しなくても,ひとは「感じとる」ことができる。
本書では,そうした作業を介した療法のスピリッツやマインドといえるものを,作業活動の考え方や使い方に関する「知」,作業療法実践のコツにあたる「技」,作業療法のセンスを伝える「理」に分けてまとめた。
ここに収められた22編は,生活機能に支障がある人に寄り添い,触れあい,援助をしながら,「作業療法とは何か?」を問い続けてきた著者の集大成とも言える。
「ひとと生活」への関わりを仕事とする方すべてに手にとっていただきたい一冊である。
序にかえて
知の章:作業療法の考え方使い方
発散的意識化を促す描画の利用
作業療法における物の利用―術後歩行困難となった接枝分裂病患者
退行現象を伴う寛解過程における作業活動の力動的観点からみた役割―精神分裂病少女の寛解過程より
作業療法と園芸―現象学的作業分析
植物という命とのかかわり
作業療法と音楽
記憶を呼び戻したピアノの役割―自殺未遂後記憶を失った分裂病患者の場合
技の章:作業療法のかかわり
作業療法過程にみられるダブル・バインド―主体性を損なわない関わりを求めて
「ふれない」ことの治療的意味―汚言に葛藤する患者の対処行動と自己治癒過程より
作業療法における「つたわり」―ことばを超えたコミュニケーション
からだの声に耳を傾けて聴くこころの声―身体化症状によりADL全介助となった少女の回復過程より
幻想と現実の分離・再統合における作業療法の機能―統合失調症性強迫性障害・認知障害の事例より
理の章:作業療法の視点
町の中の小さな畑から―慢性老人分裂病者を支える
分裂病障害にとっての集団と場
パラレルな場(トポス)の利用
「パラレルな場」という治療構造:ひとの集まりの場の治療的利用
コミュニケーションとしての作業・身体
心身統合の喪失と回復―コミュニケーションプロセスとしてみる作業療法の治療機序
作業療法とスピリチュアルケア―作業を通して生活(史)を聴く
泣く・笑う―悲哀の仕事と作業療法
愛しあい,結ぼれ,命を宿し,産み,育てる―障害がある人たちの生活支援をICFの視点から
地域の人々への啓発:気づきと学びの泉「拾円塾」
あとがきにかえて
【著者紹介】
山根寛(やまねひろし)
認定作業療法士,博士(医学),登録園芸療法士
1972年,広島大学工学部卒業
船の設計の傍ら病いや障害があっても町で暮らす運動「土の会」活動をおこなう
1982年,作業療法士の資格を取得し,精神系総合病院に勤務
1989年,地域生活支援をフィールドとするため大学に移り,「こころのバリアフリーの街づくり」「リハビリテーションは生活」「ひとが補助具に」「こころの車いす」を提唱し,生活の自律と適応を支援
「こころのバリアフリー」「リハビリテーションは生活」「ひとが補助具に」「こころの車いす」を提唱し,地域生活支援に関わる市民学習会「拾円塾」主宰,日本園芸療法研修会顧問,日本神経学的音楽療法勉強会顧問,日本音楽医療研究会世話人など,作業・活動を治療・援助手段とする多職種連携を推進
現在,京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻教授
日本作業療法士協会副会長,日本精神障害者リハビリテーション学会理事,日本園芸療法学会理事
著書
『精神障害と作業療法 第3版―治る・治すから生きるへ 』(三輪書店)
『土の宿から「まなびやー」の風がふく』(青海社)
『ひとと植物・環境―療法として園芸を使う』(青海社)
『作業療法の詩(うた)・ふたたび』(青海社)
『治療・援助における二つのコミュニケーション―作業を用いる療法の治療機序と治療関係の構築』(三輪書店)
『作業療法の詩(うた)』(青海社)
『ひとと音・音楽―療法として音楽を使う』(青海社)
『ひとと作業・作業活動 第2版―ひとにとって作業とは? どのように使うのか?』(三輪書店)
『ひとと集団・場 第2版―ひとの集まりと場を利用する』(三輪書店)
『食べることの障害とアプローチ』(三輪書店)
『伝えることの障害とアプローチ』(三輪書店)ほか
内容説明
作業療法は、治療・援助にあたる者と対象者との協同の営みであり、その過程は作業を介したコミュニケーションの成立プロセスといえる。言葉が機能しなくても、ひとは「感じとる」ことができる。ここに収められた22編は、生活機能に支障がある人に寄り添い、触れあい、援助をしながら、「作業療法とは何か?」を問い続けてきた著者の集大成。
目次
知の章―作業活動の考え方使い方(発散的意識化を促す描画の利用;作業療法における物の利用―術後歩行困難となった接技分裂病患者;退行現象を伴う寛解過程における作業活動の力動的観点からみた役割―精神分裂病少女の寛解過程より ほか)
技の章―作業療法のかかわり(作業療法過程にみられるダブル・バインド―主体性を損なわない関わりを求めて;「ふれない」ことの治療的意味―汚言に葛藤する患者の対処行動と自己治癒過程より;作業療法における「つたわり」―ことばを超えたコミュニケーション ほか)
理の章―作業療法の視点(町の中の小さな畑から―慢性老人分裂病者を支える;分裂病障害にとっての集団と場;パラレルな場(トポス)の利用 ほか)
著者等紹介
山根寛[ヤマネヒロシ]
認定作業療法士、博士(医学)、登録園芸療法士。1972年広島大学工学部卒業。船の設計の傍ら病いや障害があっても町で暮らす運動「土の会」活動をおこなう。1982年作業療法士の資格を取得し、精神系総合病院に勤務。1989年地域生活支援をフィールドとするため大学に移り、「こころのバリアフリーの街づくり」「リハビリテーションは生活」「ひとが補助具に」「こころの車いす」を提唱し、生活の自律と適応を支援。「こころのバリアフリー」「リハビリテーションは生活」「ひとが補助具に」「こころの車いす」を提唱し、地域生活支援に関わる市民学習会「拾円塾」主宰、日本園芸療法研修会顧問、日本神経学的音楽療法勉強会顧問、日本音楽医療研究会世話人など、作業・活動を治療・援助手段とする多職種連携を推進(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。