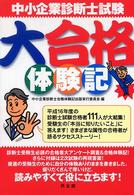内容説明
「人間関係」といえば、どの学派でも、面接者との関係、すなわち「セラピスト‐クライエント関係」(または治療者‐患者関係)が、特別に重要なものとされている。しかし、それに限らず、生活における人間関係が重要であり、それを活用することが援助に役立つというふうに考えてみよう。家族はもちろん、教師やボランティア、半専門家や非専門家などさまざまな人間関係が重要で活用可能なのである。本書では、そうした形の援助の実際についても豊富に紹介する。
目次
第1章 理論編(はじめに―不登校への多面的援助の必要性;不登校の心理臨床の基本的視点―密室型心理援助からネットワーク活用型心理援助へ;不登校理解の基礎 ほか)
第2章 実践編(スクールカウンセラーによる不登校の臨床―居場所とネットワーキング;学校内適応指導教室としての別室登校の試み;不登校の子どもへの訪問面接の方法と留意点―思春期年代に言語面接をするという観点から ほか)
第3章 不登校支援のさまざまな取り組み(NPO法人九州大学こころとそだちの相談室「こだち」の取り組み;地域における日常的な子どもの居場所;公立中学校における「夜間校内適応指導教室」 ほか)
著者等紹介
田嶌誠一[タジマセイイチ]
1951年生まれ。九州大学教育学部(心理学専攻)で心理学を学び、広島修道大学、京都教育大学等を経て、九州大学大学院人間環境学研究院教授(臨床心理学)。博士(教育心理学)。臨床心理士。日本ファミリーホーム協議会顧問。NPO法人九州大学こころとそだちの相談室「こだち」理事長。専門は臨床心理学(心理療法・カウンセリング)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しょうゆ
ヘンリー
ひろか
-
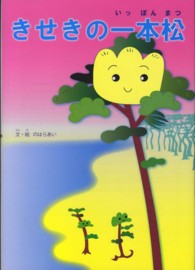
- 和書
- きせきの一本松