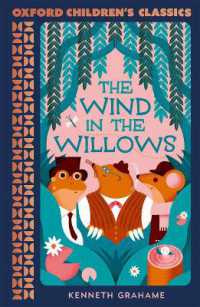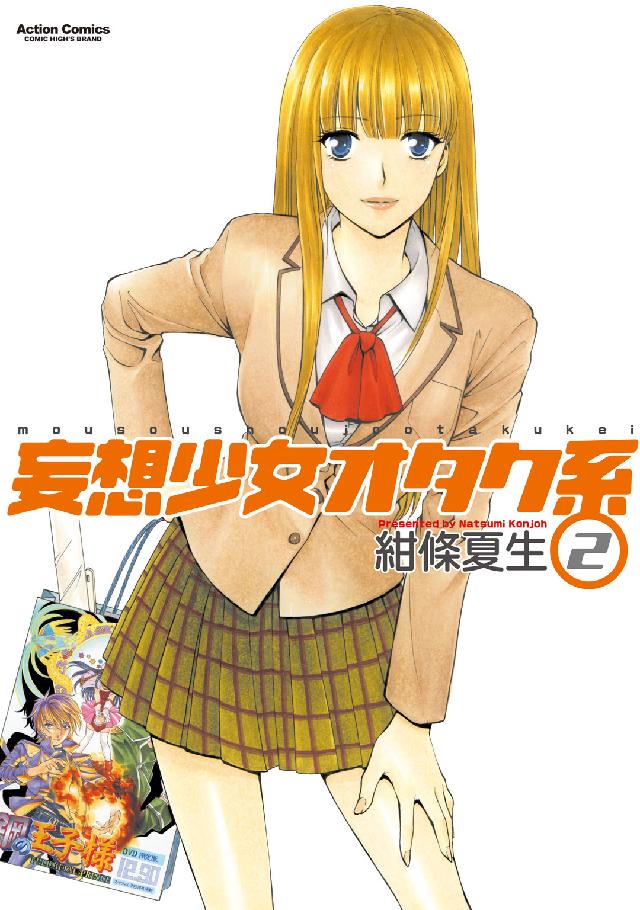- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
出版社内容情報
《内容》 引きこもりが社会的な問題として関心を集めるようになり,精神医療,臨床心理,ソーシャルワーク,ジャーナリズムなどの分野から多様な取り組みがなされているが,その問題の多面性ゆえに,共通の接点が持ちづらく,効果的な援助を難しくしているのが現状である。
本書では,ある引きこもりの経過を辿りながら,本人や家族の思いの一端を紹介し,さまざまに移ろっていく引きこもりの姿,それを取り巻く家族のイメージの共有を図る。さらに,アパシー,校内暴力,いじめ,不登校など,思春期・青年期問題のテーマの変遷を辿り比較しながら,引きこもりの系譜を捉え,「すくむタイプ」「しりごみタイプ」「症状優位タイプ」という臨床的なタイプ分けを試みている。また,「混乱期」「安定期」「ためらい期」「動き出し」という引きこもりの四つのプロセスを提示し,各プロセスごとの対応のポイントと心構え,本人・家族・援助者それぞれの役割を,実際場面に即した演習を交えて解説する。今,どのプロセスのどの位置にあるかを見極め,その時々に必要な時間をかけ,適切な取り組みを行なっていくことで,混乱を最小限にくい止め,引きこもりの閉じた環を開くことができるのである。
本人・家族・援助者が同じ目の高さから引きこもりと向きあえるように……。本人グループや親の集いの活動を通し,引きこもりの相談援助に精力的に取り組んできた著者が願いを込めて贈る,手かがりと関わりのヒント集。
蔵本信比古(くらもと・のぶひこ)
蔵本信比古著 本人・家族・援助者が同じ目の高さから引きこもりと向きあえるように……。相談援助に長年取り組んできた著者が贈る手かがりと関わりのヒント集。
内容説明
本書では、ある引きこもりの経過を辿りながら、本人や家族の思いの一端を紹介し、さまざまに移ろっていく引きこもりの姿、それを取り巻く家族のイメージの共有を図る。さらに、アパシー、校内暴力、いじめ、不登校など、思春期・青年期問題のテーマの変遷を辿り比較しながら、引きこもりの系譜を捉え、「すくむタイプ」「しりごみタイプ」「症状優位タイプ」という臨床的なタイプ分けを試みている。また、「混乱期」「安定期」「ためらい期」「動き出し」という引きこもりの四つのプロセスを提示し、各プロセスごとの対応のポイントと心構え、本人・家族・援助者それぞれの役割を、実際場面に即した演習を交えて解説する。本人・家族・援助者が同じ目の高さから引きこもりと向きあえるように…。本人グループや親の集いの活動を通し、引きこもりの相談援助に精力的に取り組んできた著者が願いを込めて贈る、手がかりと関わりのヒント集。
目次
引きこもりの姿
引きこもりオブジェクション
「引きこもり」Q&A
引きこもりの系譜
引きこもりの三つの側面
閉じた環を開く
引きこもりのプロセス
スタートラインとゴール
著者等紹介
蔵本信比古[クラモトノブヒコ]
1950年札幌市生まれ。北海道大学理学部(高分子物理化学講座)卒業。同教育学部(発達心理学講座)卒業。北海道函館、岩見沢、中央の各児童相談所勤務を経て、1995年4月より北海道立精神保健福祉センター相談部副部長。同センターにおいて、引きこもりを中心とした相談援助、思春期・青年期親の会、青年グループの運営を担当する。また、2000年3月から札幌で開催を続けている「引きこもりを考える親の集い」の支援(ボランティア)スタッフの一人としても活躍している。2001年4月より現職(北海道立女性相談援助センター判定課長)。臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。