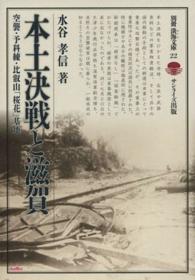出版社内容情報
海跡湖に共通して見られる砂州、湖岸低地、三角州に注目し、第1部から第3部では、上記の3種類の地形について、それぞれ最初の章で、その地形が最もよく発達している湖を紹介し、なぜそこでそのような地形が作られたのか、地形学的な視点からその謎を探る。続く章で、その地形と人々が具体的にどのように関わってきたのかについて解説する。第4部では、海跡湖の起源と生い立ちを探り、砂州、湖岸低地、三角州における人為的地形改変の影響を検討し、生物多様性の保全や自然再生の取り組み、地球温暖化と海面上昇に伴う自然災害への対応策について考察する。
目次
第1部 湖と海をへだてる砂州(サロマ湖の砂州は、なぜ日本一長いのか?;サロマ湖の砂州に付されたアイヌ語地名;人は砂州をどのように利用してきたのか?)
第2部 湖岸をふちどる段丘と湖棚(霞ヶ浦にはなぜ、多くの湖水浴場があったのか?;海跡湖の湖盆を取りかこむ更新世段丘と湖岸低地;人は湖岸をどのように改変してきたのか?)
第3部 湖奥にひろがる三角州(網走湖にはなぜ、日本一の鳥趾状三角州があるのか?;海跡湖に特徴的な鳥趾状三角州;人は三角州をどのように広げてきたのか?)
第4部 湖の生い立ち(海跡湖の起源―海跡湖は、いつ生まれどのように変化してきたのか?;ヒューマンインパクト―人為的地形改変による湖沼環境への影響;海跡湖の今後―これから海跡湖とどう付き合うのか?)
著者等紹介
平井幸弘[ヒライユキヒロ]
1956年長崎県生まれ。現在、駒澤大学文学部教授、博士(理学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
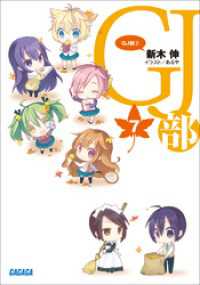
- 電子書籍
- GJ部7 ガガガ文庫