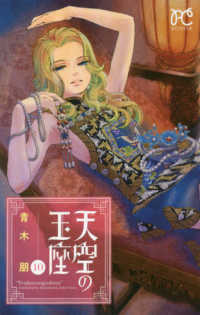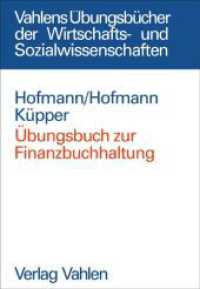出版社内容情報
朝顔の品種改良の数々、和服の小袖模様に描かれた花から当時の栽培技術を考察するなど、意外な話題から、植物の文化を描く。
フォーラムの開催趣旨(青木隆浩)
第?部 くらしの中の植物たち
1 植物の日本史を展示するくらしの植物苑(辻 誠一郎)
2 縄文人の植物質食料と木の道具(工藤雄一郎)
3 ジャパンと呼ばれた漆器(日高 薫)
第?部 季節の伝統植物
4 伝統の桜草―レスキューさくらそう―(茂田井 宏)
5 伝統の朝顔(仁田坂英二)
6 伝統の古典菊(平野 恵)
7 菊栽培の流行と小袖模様(澤田和人)
8 参勤交代と菊作りの広がり(岩淵令治)
9 冬の華 サザンカ(箱田直紀)
第?部 植物園の意義
10 植物を観賞に供する文化の誕生と発達(大場秀章)
国立歴史民俗博物館[コクリツレキシミンゾクハクブツカン]
青木 隆浩[アオキ タカヒロ]
目次
第1部 くらしの中の植物たち(植物の日本史を展示するくらしの植物苑;縄文人の植物質食料と木の道具;ジャパンと呼ばれた漆器)
第2部 季節の伝統植物(伝統の桜草―レスキューさくらそう;伝統の朝顔;伝統の古典菊;菊栽培の流行と小袖模様;参勤交代と菊作りの広がり;冬の華サザンカ)
第3部 植物園の意義(植物を観賞に供する文化の誕生と発達)
著者等紹介
青木隆浩[アオキタカヒロ]
1970年生。国立歴史民俗博物館・研究部・准教授、総合研究大学院大学・文化科学研究科・准教授。地理学、産業史が専門(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
むさみか
1
開苑20年を記念した フォーラムをまとめた内容なので 論文ですね 難しいですが たとえば 縄文時代に もうすでに 集落の近くに 栗の木を植えて活用していたこと 園芸と歴史研究がコラボした 内容は いつもとは 違った側面を知ることができます2017/05/18
めーてる
0
とても興味深い! 国立歴史民俗博物館で行われた公演会の内容をまとめた本。暮らしに身近な様々な植物の民俗的な歴史の移り変わりや、植物園時代の歴史が、分かりやすく解説されている。実際にくらしの植物苑に行ってみたいなあと思わされる本だった。2017/10/06