内容説明
環境考古学は、環境史・土地開発史・災害史をひとつの視野に入れた研究であり、「土地の履歴」を把握し、現在や未来の都市計画・防災計画に役立てようとするのが究極の目的である。過去を対象とした研究であるが、その視点は現在や未来をみつめている。本書では、縄文時代から古墳時代末までを対象に、平野研究において考古学、文献史学、歴史地理学などが援用してきた地形学、地質学、土壌学などへの誤解を解きほぐし、新たな視点から自然環境と人間活動との関わりについて検討を試みた。
目次
1 視点
2 地形環境分析
3 臨海平野の地形構造
4 縄文海進とその後の地形環境変化
5 弥生時代における環濠集落の立地と空間構造
6 埋没水田の地形環境
7 前方後円墳の地形環境
8 須恵器生産による植生破壊・地形破壊とその影響
9 まとめと展望
著者等紹介
高橋学[タカハシマナブ]
1954年愛知県生まれ。現在、立命館大学文学部教授。専門は環境考古学・地理学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
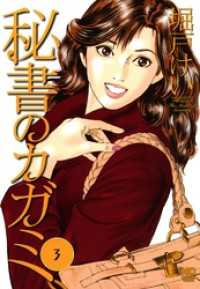
- 電子書籍
- 秘書のカガミ 3



