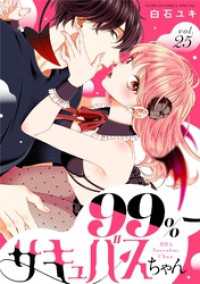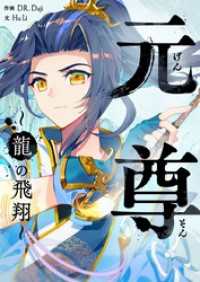出版社内容情報
沖積平野での自然災害が多発している!
先史時代から発生してきた沖積平野の災害を伴う活発な地形変化を捉えるには数百年、数千年の時間スケールが必要になるため、考古遺跡の調査から得られる情報や自然災害伝承碑の解読などは現代に生きる我々にとって極めて役に立つ。まさに「過去は、現在・未来を読み解くための鍵」といえる。
自然災害が多発する時代にあって、土地の履歴と土地に生きた人々の姿を知り、自然との付き合い方を見直すために学問的裏付けである地形環境史研究の必要性を訴え、事例をもとに研究手法・成果を解説する。
さらに、人口減少時代を迎えた日本において自然災害に配慮した新たな居住形態を模索すべきと説く。
目次
第1章 地形環境史研究とは(現生人類の空間的拡散と自然環境;平野・盆地の地形発達史研究と考古遺跡の関係;平野・盆地の地形発達史研究における古文書・古絵図の活用;ジオアーケオロジーとは何か;地形環境史研究の目的)
第2章 沖積平野の地形・地質の特徴と成り立ち(沖積平野とはどのような場所か;微地形と浅層地質から読み解く地形環境変化;沖積平野を対象とした地形環境史研究の方法)
第3章 地形環境史研究における高精度地形発達史の構築(山麓扇状地における土砂供給の時期と規模―京都盆地東縁、白川扇状地における更新世末以降の堆積環境の変遷;内陸盆地の扇状地における土砂の動態―平安京左京南部における地形環境変遷 ほか)
第4章 地形環境史研究を通じて自然災害を読み解く(遺跡からみた火山活動と人々の応答;米代川流域で発見された十和田火山915年噴火後のラハール堆積物と埋没建物 ほか)
第5章 過去と現在・未来をつなぐ地形環境史研究(人々は沖積平野をどのように利用してきたのか;「自然災害」の多発地帯としての沖積平野;グレート・ジャーニーの行方)
著者等紹介
小野映介[オノエイスケ]
駒澤大学文学部地理学科教授。1976年静岡県生まれ。名古屋大学大学院文学研究科人文学専攻博士課程後期修了。博士(地理学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手および助教、新潟大学教育人間科学部准教授、新潟大学教育学部准教授、駒澤大学文学部准教授を経て現職
佐藤善輝[サトウヨシキ]
産業技術総合研究所地質調査総合センター地質情報研究部門主任研究員。1984年愛知県生まれ。九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻古環境分野博士後期課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、九州大学大学院理学府博士研究員、日本原子力研究開発機構特定課題推進員、産業技術総合研究所地質情報研究部門特別研究員、産業技術総合研究所地質情報研究部門研究員を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。